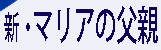越後の家を震度7の地震が襲ってひと月。この間、いろいろなことが連続してあって、正直、心身共に疲れている。
我が家がある(あった)集落の名前が、集団移転を決めた第一号として、先週はよくテレビに出てきた。
去年建てたばかりの車庫は、近所のOさんの畑を1つつぶしてもらい、年間5000円の地代で借りているのだが、その地主のOさんもテレビに出ていた。
集落全体で集団移転を決めたが、自分はやはりこの地をどうしても離れたくない。そう言って、今なお避難所には入らず、単身、車の中で寝泊まりしているという。
今までほとんど話をしたこともなかったが、骨のある人だったんだなと感心させられた。
いちばん仲のいい向かいのおばあさんは、今なお小学校の教室に他の人たちと一緒に寝泊まりしている。生き甲斐だった畑を奪われ、一気に寿命が縮んでしまったのではないかと、心が痛む。
集落が集団移転を決めても、僕たちは僕たちでまた別の場所を探さなければならない。
そんなこんなで疲れていて、新しいことを書く気力が充実しないので、3週連続で小説です。疲れているときほど掲載文章が長くなるというこの不思議。今週はついに40枚弱。編集部から「いくらなんでも長すぎ!」と怒られないかしら。
「帰還」というテーマで短編競作集を出すから書かないか、と井上雅彦さんから誘われて書いたもの。結局その短編集には採用されず、紙媒体では未発表のまま。
■
魂の帰還 たくき よしみつ
■
室温が二十四度にコントロールされたその部屋には、三人の男がいた。全裸の青年、白衣を着た医師、そして上質のガウンに身を包んだ老人。
青年は椅子に座っていたが、手足は拘束具で固定され、身動きがとれないようになっている。右手には管のついた針が埋め込まれ、そこから血液が吸い取られているところだった。
抜き取られた血液は透明な管を通り、スクリーナーと呼ばれる機械の中に吸い込まれ、別の管を通って送り出される。送り出される側の管は、青年と数メートル離れて向き合うように座っている老人の二の腕につながれていた。
青年と老人は顔がよく似ていた。親子か、祖父と孫のようにも見える。
二人の間には、中年の医師が立ち、機械の動きを見守っていた。その医師に向かって、老人が呟くように言った。
「血液ドーピングも、最近はほとんど効かなくなってきた」
「そうですか……。下手な精力剤よりは効くはずですが、何事にも限界というものがありますからね」
医師は抑揚のない声で答えた。
「言い訳はよい。新しい方法はないのか? いっそ、精液の補充はできないか?」
老人は、青年の股間に視線を向けながら言った。
青年の逸物は萎れていたが、老人のそれよりはずっと艶やかだった。
「精液は精の元ではありません。精力が生み出す結果にすぎないわけで……」
「……ああ、分かっている。言ってみたまでだ」
老人は不愉快そうに医師の説明を遮った。
その間にも、青年から抜き取られた血液は、老人の二の腕から体内へと送り込まれている。
スクリーナーのメーターを見つめていた医師がスイッチを切った。
「このくらいにしておきましょう」
スクリーナーのモーター音が止まり、部屋に静寂が訪れた。
椅子に拘束された青年は、青白い顔で老人のほうを見つめていた。表情だけではない、まるで魂が抜き取られたように、肉体全体に生気が感じられない。虚ろな視線を床に落とす青年を指さし、老人は医師に訊いた。
「
これはあとどれくらい使える?」
「そうですねえ……」
医師は青年のほうを一瞥した。
太陽を浴びたことがないような青白い肌。腹には数か所の手術痕がある。
「肝臓はまだ完全には回復していません。腎臓はもう一つ残っていますが、これを取ってしまうと延命装置にパイプでつないだまま生かすことになりますから、一気に寿命が縮むでしょう。うまく使えば、まだ十年は大丈夫だとは思うのですが」
「これが使えなくなる前に、新しいバックアップを作るか」
「別のを解凍なさるんですか? でも、今からですと、臓器が使えるようになるまでには最低でも十数年はかかりますよ」
「ああ、分かっている。その前に俺が死んだのではバックアップにならんからな。ただのバックアップとしてではなく、違う使い方を考えているところだ。いずれにせよ、アビバと相談して決める」
「またアビバですか。呪術と医学を混同されては……」
「混同ではない。融合だ。おまえら医学者は、魂の存在を無視しすぎている。DNAの情報ですべてが説明できるなら、まったく同じ遺伝子情報を持つ一卵性双生児の人生はどうなる? 一卵性双生児は、生物学的には完全なクローンだ。しかし、クローンといえども、別々に考え、別々に感じ、別々の生を生きていくではないか」
「魂……ですか? まあ、その通りかもしれませんね」
まさに魂を抜き取られた、肉体の補修パーツとしての青年を一瞥し、医師は皮肉な笑みを浮かべた。
「魂の存在を説明できぬ以上、俺はおまえたちの医学とやらを全面的に信じるわけにはいかん。最後の卵をどう使うかは、俺が決めることだ」
そう言うと、老人は自分で輸血パイプを外し、部屋を出ていった。
老人の名はイル。
彼は「大君」と呼ばれるこの国の最高権力者であり、国民にとっては神同様の存在だった。国中のあちこちに彼の肖像が飾られ、人々は声を揃えて彼の名を称える。
〈偉大なる大君イル様。宇宙の神秘に触れるお方イル様。私たちはいつでもあなた様のご指導に従い、人間としての尊厳を全うします……〉
長期化した飢饉で、地方では餓死者が絶えないというのに、軍備拡張路線を改めない最高権力者を批判する者はいない。
イルは今年八十歳になるが、風貌は六十前後くらいにしか見えない。しかし、イルは自分が六十歳くらいにしか見えないことには満足しておらず、六十に見えてしまうことに失望していた。
強壮剤、回春薬、コラーゲン、栄養食品……どんなものを用いても、老いというものは止められず、多少遅らせることができるだけなのか? 老いの先に待っている死は避けようがないものなのか?
そう考えると、眠れないほどの恐怖に陥る。老いと死の恐怖を紛らすため、毎晩、媚薬を使って女と戯れ、酒と薬で思考を麻痺させながら眠りにつく。
イルの父親・ギル、つまり先代大君も、不老長寿を執拗に追い求めた男だった。老いと死を異常に恐怖し、自分の若さを保つためには、どんな手段をも使った。不老長寿の秘薬と聞けば、家臣に命じ、世界中から集めさせ、試してみた。
それだけでは飽きたらず、晩年は、西洋最先端医学の専門家や遺伝子工学の科学者なども呼び寄せた。もちろん、彼らを満足させるだけの富と研究施設を与えてのことだ。
宮殿敷地内の地下には、先代が密かに建設した最先端生化学研究所がある。「闇の間」と呼ばれるその研究所では、生きた人体をふんだんに使って様々な研究が行われていた。
人体を使った遺伝子組み替え実験をできる研究所など、そうそうあるものではない。この国に招聘された外国人研究者たちは、莫大な報酬よりもむしろ、密かに生体実験ができる特殊環境に惹かれたのだった。
ギルは人一倍好色だったが、子供には恵まれなかった。
そこで、ついには人工授精による後継者作りに踏み切った。世界最高レベルの技術を誇る「闇の間」の科学者や医師団にとって、人工授精などはごくごく簡単なことだった。
しかし、その際、ギルは単純な人工授精では満足しなかった。自分とまったく同じDNAを持つクローンを作ろうとしたのだった。
有名な羊のドリーは、受精卵ではなく、体細胞から抜き取った核を未受精卵に移植して作られた「体細胞クローン」とされている。羊でできることが、人間でできないはずはない。モラルの問題とやらで、人間では実験されていなかったにすぎない。
この国では、モラルという言葉は大君・ギルが自由に定義すればよかった。
ギルは闇の間の科学者たちに命じて、自分のクローンを作らせた。それがイルである。
つまり、イルはギルの子供というよりは、遅れて生まれてきた一卵性双生児のようなものだった。
遺伝子情報が同じ生物に自分の権力を引き継がせる……それがギルの野望だったのだ。言い換えれば、自分の存在を永遠に残したいという妄想と言えるかもしれない。
理由はどうであれ、とにかくイルはこの世に誕生した。
しかし、イルの誕生には、もう一つ秘密があった。
体細胞クローンによる受精卵は、一つではなく、複数作られていたのだ。ギルはそのうちの一つを世継ぎとして誕生させ、残りは冷凍保存させた。
これは、万一クローンの世継ぎに何かあっても、「バックアップ」を取っておけば安心だという発想からだった。
だが、二人以上のクローンが同時に生を受けることは好まなかった。双子や三つ子が同時に生きていれば、いっぺんに暗殺されたり、争乱に巻き込まれて死に絶える危険性がある。あるいは、互いに反目し合って殺し合うかもしれない。しかし、冷凍保存された受精卵ならば、そうした危険はないと考えたのだ。
世継ぎのイルがギルのクローンであり、しかも研究所の冷凍庫にはさらに同じ遺伝子情報を持つ「バックアップ」の受精卵が複数存在するという秘密は、大君を取り巻くごく一部の重臣たちしか知らなかった。
ギルは八十歳にして膵臓癌で死んだ。死の床で、クローン跡継ぎのイルにこう呟いた。
「私がここに生きている限り、おまえは私ではない。私も、もう少し後の時代に生まれていれば、永遠に生きる手段を得られたかもしれない……」
そう言い残して死んでいった先代の姿を、イルは今でもよく覚えている。
先代の血を引く……いや、先代とまったく同じ遺伝子を持つだけあって、イルもまた、若いうちから生への執着が強かった。
生まれつき病弱だったイルは、今までに何度も大病をした。腎不全、白内障、肝機能障害……。だが、その度に「闇の間」の医師や科学者たちによる最先端医療技術のおかげで生き延びてきた。
四十代に入り、自分の精力の衰えを痛感したとき、イルは自分の「バックアップ」をこの世に誕生させ、パーツとして活用し始めた。
自分とまったく同じ遺伝子情報を持って生まれてくる弟を、「人間」としては迎えない。思考を麻痺させ、自由も奪った状態で、ただ肉体として生理的に生きることだけを許した。なぜなら、
それは「バックアップ」にすぎなかったからだ。バックアップには独自の人生は許されない。
闇の間の科学者たちの手により、冷凍受精卵の一つが生を与えられた。名前を持つことさえ許されず、
それはただひたすら、イルの肉体の予備パーツを供給する存在として生育された。
歳をとると共に、イルの持病は悪化していった。
腎不全や肝機能障害もぶり返し、もはや臓器移植しか効果的な治療法がないと診断される度に、この世に後れて生まれてきたイルの弟は、肉体の一部を奪われていった。十五歳で角膜を取られたのを皮切りに、十八歳では腎臓を片方摘出、二十歳では肝臓の半分も切り取られた。
そしてときには、老いたイルに精力をみなぎらせるため、血液も抜き取られた。
スポーツ選手が自分の血液を抜き取ってストックしておき、競技の前に身体に注入し、驚異的なスタミナを得る「血液ドーピング」という手法がある。それを、イルは同じ遺伝子を持った弟の身体を利用して行っていた。
自分の実年齢よりも若い肉体から抜き取った血液は、どんな精力剤よりも効果が高かった。
それでも、イルは確実に歳をとっていった。
精力剤を飲み、血液ドーピングをしても、今では、セックスは週に一度がやっとだった。それも、完全な勃起を得られることは少ない。精液のほとばしりも勢いを失い、だらだらと流れ出るのがやっとだ。もちろん、八十歳という実年齢を考えれば、それすらも驚異的なことなのだが、イルは失望していた。
何よりも、生への意欲が減退していた。死は相変わらず怖かったが、若さを誇れない生活には魅力を感じない。「死なない」ことよりも、若返ることを切望していた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
広い寝室の中央には、贅を尽くした円形の寝台があった。どんな意味があるのか分からないが、水の代わりにバージンオリーブオイルが充填されたウォーターベッド、いやオイルベッドだ。縁には麝香や象牙材を駆使している。寝具は、最高級の絹と白鳥のダウンだけを使っている。
その上に、イルは全裸で横たわっていた。
夜伽の女官が三人、円形ベッドを取り巻いていた。
一人はイルの膝を舌で愛撫し、別の一人はイルの乳首に細い指をそっと這わせている。この二人は三十前後だろうか、肌が透ける薄衣だけをまとった半裸だった。
残る一人は、枕元に座り、イルの右手を軽く握っているだけだった。この女は他の二人よりは明らかに一回りは年上に見える。身にまとっているものも、地味なガウンだった。
「なあアビバ。時間を戻すことはできるか?」
イルは、枕元に乳母のように付き添う女に訊いた。
「いいえ。時間は決して戻すことはできません」
「私はやはり死ぬのか?」
「はい。肉体は滅びます」
「どんなことをしても、死は避けられないものなのか?」
「はい。肉体が老いて朽ちることは、どんなことをしても避けられません」
アビバと呼ばれた中年女は、淡々とした口調で答えた。
彼女は隣の大国北部の山奥から呼ばれた呪術師である。遠くヒマラヤの麓に、不老不死の秘密を知る呪術を駆使する部族がいるという噂は、先代のギルの耳にも届いていた。ギルは密かにその部族を探させていたが、ついに自分が生きているうちには接触することができなかった。
イルの代になっても、その部族を探す特殊部隊は仕事を続けていた。そしてついには探し出し、部族長の娘の一人をこの国に招き入れることに成功したのだった。
アビバが教育係の老婆と一緒にこの国へ呼ばれたのは、まだ十二歳のときだった。すぐにイルの側室となり、その後、ずっとイルのそばに仕えてきた。
教育係の老婆は、部族に伝わる秘伝・秘術をアビバに仕込み、数年前、他界した。
アビバは普段、ほとんど口を利かなかった。地味な顔立ちで、側室とはいうものの、イルの寵愛を受けることもなかった。
イルの話相手として呼ばれるようになったのは、ごく最近のことだ。イルも、さすがにこの歳になると、美貌や器量よりも、人生を語れる相手を求めるようになったのだった。
「では訊くが、肉体が滅びた後、魂は残るという話は本当か?」
イルはアビバの手を握り返して言った。
「魂は残るのではなく、帰るのです」
「帰る? どこへだ」
「その魂がふさわしい場所に」
「分からんな」
「イル様は、物事を肉体で、つまり脳でお考えになっています。魂は、肉体で考えていても見えません」
「そのような禅問答は嫌いだ。もう少し分かるように話せないのか」
イルは、むずかる子供のように言った。その拍子に片足が曲がり、膝を舐めていた女官の頬を打った。女官はかすかに顔をしかめたが、何事もなかったかのように、すぐまた愛撫のタイミングを探し始めた。
「例えば、魂は水のようなものです。目には見えませんが、空気の中には、無数の水の粒が隠れていますでしょう?」
「水蒸気のことか?」
「名前はどうでもいいのです。水は空を登り、宇宙の永遠なる冷気に触れ、その深遠さにおののいて身を縮め、雨となって地に戻ってきます。そして例えば、稲の根に吸われ、米粒の中に宿ります。そこがふさわしい場所だったからです。
米粒はイル様に食べられ、糞として捨てられます。糞になってしまえば、どんな魔法を用いようと、米粒には戻りません。でも、米粒に宿った水は、米粒が糞に変わった後も、形を変え、どこかで生きています。そして時が来ればまた空を登り、雨となって戻ってきます。再び米粒の中に宿ることもあるかもしれません。
イル様の肉体は米粒と同じです。水が米粒に宿るように、魂が宿って、命を得ます。肉体が朽ち果てて形を失っても、宿った魂は、水が天に昇り、また土の上に降ってくるように、いつかまたふさわしい場所に戻ってきます」
「まあ、よくある霊肉二元論のたとえ話だな。問題は、俺の実体は米粒のほうなのか、そこに宿った水のほうなのかということだ。俺の肉体が滅んでも、魂はどこかに帰り、再び新しい肉体に宿ったとしよう。そのとき、今の俺はもういないのか? 俺が今ここでアビバと語らっている記憶は消されているのか? 国中の者をひれ伏させる権力はなくなっているのか?」
「普通はそうです。形を引きずらないからこそ、水は透明なのです。汚れを漉した後に天に昇り、地に降るからこそ雨は尊いのです。もしも雨が濁ったままだったらどうなるでしょう。雨は地を汚していきましょう」
「一般論ではなく、俺の場合のことを具体的に知りたい。今『普通は』と言ったな。普通ではない場合もあるのか? 今の俺の記憶や意識を消さないまま、新しい肉体に宿ることは可能なのか? 他の魂はどうでもよい。今、俺の肉体に宿り、俺を俺たらしめている魂を、今の俺の記憶を残したまま次の肉体に宿らせることはできるか?」
矢継ぎ早に問われ、アビバは少しの間沈黙したが、躊躇いがちに答えた。
「できなくはありません」
「それが知りたい。今の記憶や知力を持ったまま、指定した肉体に宿る方法を知りたい」
イルは上半身を起きあがらせ、アビバの手を握った。
その気迫におののき、二人の女官は愛撫をやめて身を引いた。
「ご自分の庭にだけ、色の付いた雨を降らせよ、ということですね?」
アビバが問い返した。
「そうだ」
イルは強い口調で言った。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
アビバは「できる」と言った。
現世の記憶と意識を消さぬまま、新しい肉体に魂を宿らせることは可能だと言った。
にわかには信じられなかったが、やがて確かめるべき時は訪れた。
イルは父親同様、膵臓癌に冒されていたのだった。
対処療法には限界があり、バックアップである弟の肉体から臓器を摘出し、移植する手術が行われることになった。
手術の前、イルは医師団と家臣たち、そしてアビバを呼んで命じた。
「俺ももう歳だ。この手術に耐えられるかどうか、自信がない。
もしも俺が死ぬようなことがあれば、ただちに冷凍されているクローン受精卵の一つを解凍し、この世に俺と同じ遺伝子情報を持つ赤ん坊を誕生させよ。
アビバは、その赤ん坊に俺の記憶と意識を植え付けるよう、術の粋を尽くせ。俺は、今の記憶を持ったまま、もう一度この国の大君としての人生をやり直す。俺の新しい肉体が俺の意識を引き継ぐにふさわしい程度に成長するまでは、アビバに俺の全権を委譲する」
医師団や家臣たちは、イルのこの命令を受け入れた。
膵臓の移植手術は、一旦は成功した。しかし、引き替えに「バックアップ」であるクローン弟の命は消えた。
イルは術後、順調に回復するかに見えたが、数日後、容態が急変した。薄れゆく意識の中で、イルは必死に叫んだ。
「あの計画を実行しろ。アビバ、今こそおまえの力を見せてみよ」
アビバはイルの寝台の脇に立つと、医師団や家臣たちに、威厳に満ちた声で命じた。
「全員、この部屋から出なさい。私は今から大君様の魂がご無事に帰るべき場所に帰れるよう、祈祷の儀に入ります」
もとよりイルから命じられていたことだったので、医師団も家臣たちも素直に従った。
医師団はすぐ、冷凍保存されていた受精卵を解凍し、若く健康な女性の子宮に着床させた。
厳重な監視態勢の下、受精卵は赤ん坊へと細胞分裂していった。
人払いをした部屋で、アビバはイルのしなびた身体を見下ろしていた。
白いサリーのような服を脱ぎ、アビバは全裸になって跪くと、イルの身体の中心部に両手を伸ばした。
〈サライウンケンアビカモスランドフィルウンヌケンゲンジョウ……〉
低い声で唸るように祈祷の文句を唱える。
アビバの細い指が、縮こまって存在を隠しているイルの逸物に伸びた。
〈セリンジョボヌンケンアビラソワカシカジリンサライウンケン……〉
一人綾取りをするように、アビバの指がイルの男根の上で妖しく動く。しかし、直接触っているわけではない。触れるか触れないかという間合いを置き、うねるように動き続ける。
祈祷の声に力が入るに連れ、アビバの身体のあちこちで、肉がさざ波のように脈打ち始めた。張りを失いかけている乳房は小刻みに揺れ、脂肪のない背中には筋が盛り上がる。
やがてアビバの全身はうっすらとピンク色に輝き始め、それに呼応するかのように、イルの股間にははっきりと隆起の兆しが現れた。
アビバの全身全霊の祈りが、死にかけたイルの老体を呼び覚まし、最後の生命活動を促しているかのようだ。
無数の女の身体を射抜いてきたイルの逸物が、少しずつ頭をもたげ始めた。
〈サライウンケンアビカモスランドフィルウンヌケンゲンジョウセリンジョボヌンケンアビラソワカシカジリン……〉
アビバの身体はさらに赤みを増し、祈祷はいつしか喜悦の声のようにうわずっていった。全身が細かく震え、乳頭は堅く突き出し、絶頂の時が近づいていることを示していた。
自らも快感の高まりを感じながら、アビバは今、今まで絶対的な支配者だったこの男を、完全に支配していた。
横たわったままのイルの肉体からは、股間のシンボルだけが、全盛期にも見せなかったほどの堅さを得て、塔のようにそそり立っていた。まるで、そこだけがまったく別の物体のように。
〈……ウンケンアビカモスラン……〉
アビバの祈祷の声がふっと吐息のように消え入り、全身が硬直した。
アビバは蝋人形のように動きを止めていた。部屋には静寂が戻った。
と同時に、イルの硬直した男根の先から、白い煙のようなものが出てきた。
煙というには形がはっきりしすぎている。胃のレントゲン検査のときに飲まされるバリウムに似ている。その白い物体が、ふわふわと部屋の天井のほうに登っていき、中空で止まった。
ゆったりと宙に浮かぶ白い物体に向かって、アビバは最後の力を振り絞るようにかすれた声で告げた。
「おまえが帰るべき場所が用意されている。記憶も意識も閉ざすことなく、帰るべき場所へ行け」
白い不定形の物体は、しばし迷ったように漂っていたが、やがてどこかに吸い込まれるように消えた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
気がつくと、全裸の女が寝台に寄り添っているのが見下ろせた。
見下ろす?
自分はどこに位置しているのだろうか?
寝台には老人が横たわっていた。それが自分だと気づくまでには、少しだけ時間を要した。老醜が気になり、最近では自分の姿を鏡に映すことをしていなかったからだ。
それが自分自身の肉体なのだと認めてからは、すぐに状況を把握できた。これがあの「幽体離脱」というものなのだろう。つまり、自分は死んでしまった、あるいは、今、死のうとしているのだ。
部屋を見下ろしている自分は、肉体を離れた魂なのか?
イルは自分の記憶を遡った。
自分が誰なのか、どんな一生を送ってきたか、はっきりと覚えていた。意識も記憶もまだ消えてはいない。
ということは、アビバはうまくやったのだろうか。
魂に今までの意識と記憶を付着させ、遊離させることに成功したのだろうか?
その疑問は長くは続かなかった。
部屋の光景はすぐに薄れて、消えてしまった。
真っ暗な闇に閉ざされ、意識だけが孤立する世界が訪れた。
触感は何もない。身体がないのだからあたりまえだろう。
光だけではなく、音も臭いもない。
「ここはどこだ?」
イルは試しに問いかけてみた。
もちろん、声は出ない。意識の中で、多分この「世界」をコントロールしている何者かに向かって問いかけてみた。
〈ここは魂が帰ってくる場所です〉
ほどなく、何者かがそう答えた。アビバの声に似ていた。
「アビバなのか?」
〈いいえ。私は何者でもありません。あなたが知っているアビバという女だと感じるなら、それはあなたの意識が引きずってきた記憶がそうさせているだけです〉
確かにアビバの声だった。いや、正確には「声」ではないかもしれないが、イルにはアビバの声として認識された。
誰でもいい。答えてくれるならそれでいい。
「ここはどこだ?」
イルはもう一度訊いた。
〈言ったでしょう。魂が帰る場所です。魂はここで濾過され、透明になって、次の場所に宿る時を待つのです〉
「次の場所へ行けるのはいつだ?」
〈たった今かもしれませんし、永遠と呼んでもいいくらい先のことかもしれません。でも、待っている魂に意識はありませんから、どちらも同じことなのです。一瞬も永遠も、この場所では同義です〉
「だが、俺はこうして意識がある。考えてもいる」
〈それはあなたがそう望んだからです。アビバという女が、あなたの願いを叶えるために呪術を施しました。あなたは今、意識と記憶を消さないまま、魂になっています〉
「俺はこれからどうなるんだ?」
〈待つだけです。あなたの魂にふさわしい次の場所が見つかるまで〉
その答えの意味を理解したとき、イルの意識は底なしの恐怖に落ちた。
待つ?
この何もない闇の中でか?
光も音も臭いもない。なんの感覚もない無の世界で、意識だけが目覚めたまま、もしかしたら永遠に近い時間を過ごさねばならないというのか?
冗談じゃない。話が違うではないか。
「確かに俺は、記憶と意識が消えることを拒んだ。だがそれは、新しい肉体に戻るという前提でだ。今頃、俺と同じ遺伝子情報を持つ冷凍受精卵が解凍され、生命を授かろうとしているはずだ。俺はその肉体に、今こうして思考している『この意識』として入っていきたい。肉体だけを交換し、記憶は蓄積させていく人生を続けたい。アビバにはそれを命じたんだ」
イルは闇の中で必死に訴えた。
〈分かっています。アビバは、忠実に、あなたのその願いを込めて祈りました。多分、望みは叶えられるでしょう。ただし、この世界では、時間というものが意味をなしません。あなたが今までいた世界のように、時間が直線的に進んでいるわけではないのです。あなたは、願い通り、今までの意識を持ったまま、同じ遺伝子情報を持つ若い肉体に入り込めるでしょう。でも、それは永遠と言っていいくらいずっと先のことかもしれません。無色透明になった魂にとっては、永遠は一瞬と同じことですが、意識を持ったまま魂になっている今のあなたには、もしかしたら長い時間だと感じられるかもしれませんね。耐え難いほど退屈な時間かもしれません〉
「それは困る!」
「困ると言われても、この世界ではそうなのです。時間を超越した魂の場所に、時間の所産である意識や記憶を持ち込むこと自体、無理があるのです。どうしても記憶を残したまま魂の世界に入るというならば、魂は帰る場所を失い、ある一つの肉体を巡って永遠にループしてしまうかもしれません」
「ループする?」
〈同じ性質を持った肉体に何度も宿り続けるということです〉
「それは構わない。その度に肉体が若返るならな。むしろ、それこそ俺が望んだことだ」
意識は変わらないまま、記憶を重ね、肉体だけ定期的に若返るなら、それは即ち、永遠の命を得るのと同じだ。
「頼む。こんな何もない場所で、気が遠くなるほど待たされるのはかなわない。俺が戻るべき肉体はすでに用意してある。同じ遺伝子情報を持った受精卵から生まれた肉体だ。そこにこの意識が入っていけば、俺は人生をやり直せる。今すぐ、新しい肉体に戻してくれ」
答えはなかった。
「どうしたんだ? 返事をしてくれ。まさか、話相手もないまま、俺をこの闇に閉じこめるつもりではないだろうな」
イルは叫んだ。声は出ないが、意識の限り叫んだ。
だが、闇の中からは、二度と返答はなかった。
光も音もない。触感も臭いもない。意識だけが明確に存在しているだけの世界に、イルは閉じこめられた。
どれだけの時間が経っただろうか。ほんの数秒かもしれないし、数億年かもしれない。
あの世界での時間という概念は、確かにこの無の世界ではなんの意味もなさなかった。
イルが今望んでいることはたった一つ。意識を失うことだった。
それが無理なら、何も考えられないほど徹底的に発狂したかった。
苦しみも退屈も感じないほどに意識を麻痺させたかった。
しかし、それはかなわなかった。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
さらにどれだけの時が経っただろうか。
イルの意識の中で時間という概念が意味を失った頃、ようやく「そのとき」がやってきた。
闇の奥に、一条の光が見えた気がした。
イルの意識は、その光のほうにどんどん吸い寄せられていった。
生まれ変われるのか? ようやく肉体に戻れるのか?
イルは狂喜した。
もう贅沢は言わない。なんでもいい。ハツカネズミでもミミズでもバクテリアでもいい。この何もない闇という地獄から抜け出せるなら、肉体を得られるなら、今よりははるかに幸せなことだ。
イルの意識は、強烈な光の中に吸い込まれた。
やがて、遠い昔に置いてきたあの感覚が少しずつ戻ってきた。
肉体。
そう、肉体だ!
一瞬、窮屈で閉ざされた檻の中に入れられるような恐怖感が襲ったが、宙ぶらりんのまま、永遠という悪夢に囚われていた今までと決別できる喜びのほうがはるかに大きかった。
肉体を得たという感覚は、少しずつイルの意識に戻ってきた。だが、まだ何も見えない。
やがて音が聞こえるようになった。ザザーッという、放送を終えたラジオのノイズのようなものが聞こえる。
液体と密着した肉の感触。
そうか、これはもしかしたら胎内なのか? 俺は胎児として成長しているところなのか?
その過程でも、イルの意識は昔のままだった。つまり、あの国の最高権力者として君臨していたときの記憶、自分がイルであるという認識を持ったままだった。
思考力と記憶を持ったまま胎児の肉体に宿るということは、あの無の世界に閉じこめられたときと同じくらい苦しいことだった。
イルとして生き、イルとして死んだときと同じ意識、時間感覚を持ったまま胎児になったのだ。地震で壊れた家の下敷きになり、地中に閉じこめられたようなものだった。しかも、自殺するわけにはいかず、栄養は強制的に取らされている。
苦しい。気が狂いそうだ。
しかし、待つしかなかった。
発狂する寸前になりながら、イルはひたすら待った。
胎内にいるとすれば、少なくともバクテリアや昆虫ではなさそうだ。多分、今度も人間だろうという確信を持ち始めた。
そしてついに、外界に出ていける時が訪れた。
全身を押しつける肉の圧力に耐えながら、イルは歓喜の中にいた。
ようやく出られる。俺の第二の人生が始まる……。
身を包んでいた羊水が流れ出す感触があり、全身が冷気に包まれた。イルは喜びのあまり、思い切り声を上げて泣いた。
誰かに取り上げられる感覚。
「おめでとうございます。元気な赤ん坊です」
医師だろうか、どこかで聞き覚えのあるような声が聞こえた。
「大君に似ていますね。同じ遺伝子を持っているからあたりまえですけれど」
別の男の声がそう言った。
そうか。うまくいったのだ。俺は過去の意識を持ったまま、俺と同じ遺伝子情報を持つ新しい肉体に帰ってきたのだ。
思い出したぞ。あの医師の声を。ということは、ちゃんとあの時間に戻ってきたのだ。新しい肉体を得て。
イルは喜びのあまり、大声で泣き叫んだ。
「元気ですね。こんなに大声で泣く赤ん坊も珍しい」
医師の一人が言った。
「そうだな。しかし、奇妙なものだな、自分のクローンの誕生をこうして目の当たりにするというのも」
そう告げた声にも聞き覚えがあった。だが、医師団ではない。
これは……。
「いいな、これはあくまでも俺のバックアップだ。世継ぎとして育てるわけではない。臓器や皮膚のストックなんだ。物心つく前に、思考を鈍らせる処置を施してくれ」
これは……俺の声だ。
イルは今、はっきりと悟った。自分が置かれている状況を。
記憶の彼方で、いつだったか闇の中で聞いた声が甦った。
〈時間を超越した魂の場所に、時間の所産である意識や記憶を持ち込むこと自体、無理があるのです。どうしても記憶を残したまま魂の世界に入るというならば、魂は帰る場所を失い、ある一つの肉体を巡って永遠にループしてしまうかもしれません〉
ループする?
永遠に繰り返す?
これを……か……?
あまりの恐怖に、イルはもう、泣き叫ぶこともできなかった。
(執筆 2000年1月17日 紙媒体未発表 WEB初出
文藝ネット 2003年1月6日)

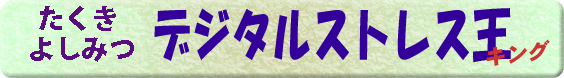


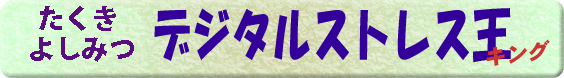



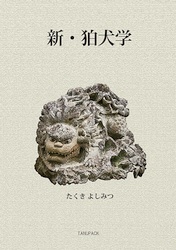
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)