テレビのチャンネルを変えていたら、衛星放送のどこかで、たまたま鈴木康博さんのライブをやっていた。ずいぶん顔が変わっていて、一瞬、高田渡かと思ってしまった。
鈴木康博といえばオフコース。僕が音楽を本気で始めたきっかけはオフコースだった。
1969年。鈴木康博、小田和正、地主道夫という聖光学院の3期生3人で結成したフォークグループ、オフコース(その頃は「ジ・オフ・コース」と、定冠詞つきで名乗っていた)は、ヤマハのライトミュージックコンテスト・フォーク部門に東北地区から出場(小田さん、地主さんが東北大学の学生だったため。鈴木さんは東工大で、練習は仙台と東京を行ったり来たりしながらやっていたらしい)。全国大会にまで勝ち進み、第2位になった。
そのときの1位が赤い鳥で、メンバーは後藤悦治郎、平山泰代、大川茂、新居(後の山本)潤子、山本俊彦の5人。ちなみに、ザ・フォーシンガーズというのも出場していて、入賞はできなかったが、その中には後のチューリップの財津和夫もいた。
赤い鳥は、後藤、平山が結婚して紙ふうせんというフォークデュオを結成。残りの3人はハイファイセットというコーラスグループを結成して別々の道を行くことになる。
初代オフコースは、鈴木さんがウッドベースとリードヴォーカルを担当していた。小田さんと地主さんはナイロン弦のギターを弾いていて、ピーター・ポール&マリーのコピーや、バート・バカラック、ビートルズ、ニール・セダカなどのヒット曲をPPM風にアレンジしたものをやっていた。あの頃のオフコースを知る人たちの多くは、「オフコースはアマチュア時代がいちばんよかったよね」と言う。実は僕もそうした「アマチュア時代のオフコースファン」のひとりだ。
僕が初めてオフコースを聴いたのは、1969年の秋。ライトミュージックコンテスト・フォーク部門全国大会で2位になった2日後、彼らが母校の聖光学院の学園祭に「飛び入り凱旋」し、閉会式の前に小一時間ほどのコンサートをやったときだった。
講堂にあったのは、エコーも何もかからない素のスタンドマイクが3本だけ。鈴木さんのウッドベースはマイクなしで生音だけ。小田さんと地主さんはヴォーカル用1本、ギター用1本のマイクを左右から挟むような形で演奏した。
僕はこのとき中学2年生。客席の中にいて、彼らのハーモニーの素晴らしさに鳥肌が立つほど感動していた。世の中にこんなに美しいコーラスがあるのだろうかと驚いた。
翌日、教室で「俺と一緒にフォークバンドやるやつ手を挙げて!」と叫んでいた。すぐに手を挙げたのが3人いた。みんな昨日のオフコースの演奏に感動し、同じ思いだった。
オフコースはPPMのコピーバンドだったが、僕らはオフコースのコピーバンドをやったので、PPMもビートルズもバカラックも、オフコースの演奏を通じて初めて知った。オフコースのレコードデビュー曲『群衆の中で』は、ライブバージョンの間奏フレーズまでコピーしたものだ。
コピーするために、オフコースのライブがあると聴けば、どこへでも出かけていき、持参したカセットテープレコーダー(当時はまだでかかった)に盗み録りした。
一度、オフコースが聖光学院のPTAや職員たちのクリスマス会に呼ばれたことがあった。職員室の奥で演奏するらしいと聞きつけ、どうしても聴きたかった僕らは、放課後、職員室とドア1枚でつながっている階段教室というところに忍び込み、息を潜めてその時を待った。
やがて守衛さんが回ってきて、僕らが隠れていることを知らず、外から鍵を閉める。それを確認してから、職員室につながっているほうのドアのところに行き、気づかれないようにほんの数センチだけドアを開けて、聞こえてくるオフコースの演奏に耳を傾けた。
演奏会が終わったのは夜になってからだった。階段教室の施錠されたドアを内側から開け、まっ暗な校舎を泥棒のように足音を立てずに抜け出し、帰宅した。
あのとき、職員室の裏側に息を殺して潜んでいた生徒が4人いたことは、僕たち以外は誰も知らない。翌朝、守衛さんは、階段教室のドアが施錠されていないのを知って、不審に思ったに違いない。
オフコースが自宅で練習しているテープというのも持っている。
聖光のK先輩が持っていたのをコピーさせてもらったのだが、これは小田さんの実家である小田薬局の二階で練習したときに、オープンリールテープを回して録音したという代物。
小田さんが、ある女の子にプレゼントしたらしいのだが、その女の子はオープンリールデッキなど持っておらず、K先輩に「このテープあげるからコピーして」と頼んだらしい。それを僕がまたコピーさせてもらったのだ。
このテープの最後には、他の二人が帰った後に小田さんだけ残って、何やら作曲している様子が録音されている。ララララーラーと、スキャットだけで何やら歌ってはガチャっと切っている断片がいくつも続いているのだが、少しずつメロディーが変わっていき、まとまっていくのが分かる。どう考えても作曲している「メモ」だろう。とてもいいメロディーなのだが、その後、オフコースのオリジナルでこのメロディーを聴いたことはない。もしかして、小田さんも、この作曲しかけたモチーフについてはすっかり忘れているのかもしれない。
オフコースはその後、プロになる際に地主さんが抜け、聖光の2年後輩(つまり5期生)である小林和行さんがベーシストとして参加。しばらくして小林さんも抜け、ふたりに戻り、その後、もう3人加わって5人のコーラスグループになって、東海林修作詞・作曲の『おさらば』という曲で東京音楽祭に出場したりしていた。
杉田次郎のバックとして「杉田次郎とオフコース」なんて形でやっていた時期もある。
ドラム、ベース、エレクトリックギターの3人が加わってからはすっかり「小田和正バンド」の色が濃くなり、僕はどんどん興味をなくしていってしまった。
オフコースに限らず、20代の頃、若さに任せて作ったラブソングを、50代になっても歌っているフォークシンガーたちを見ると、とても複雑な気持ちになる。僕自身は、日本語のラブソングに気恥ずかしさを感じて、30代くらいから徐々にボサノバやジャズに傾倒していった。自分が20代に書いたラブソングを今歌うには、相当な気力と勇気が必要だ。なんといっても、歌詞が……ねえ。
歌詞に限らず、詩というのは「言い換え」だと思っている。悲しい、愛しい、懐かしい、好きだ、切ない……といった感情を、別の言葉や表現に言い換えて歌にするのがソングライターの芸であるはずだが、日本のフォークやニューミュージックと呼ばれている歌は、その基本的な芸がほとんどできていない。若者の拙いラブレターをそのまま歌ってしまっているようなものが多い。(例外はユーミンで、彼女の作詞家としての能力はピカイチだろう。)
僕には詩人の才能がない。これはかなり前から自覚している。かといって、素晴らしい作詞家にも出逢えなかった。
歌がない音楽をやるために、
ギターデュオKAMUNAを結成したのだが、人からは「ギターデュオなんていう、およそ売れそうもないジャンルに、よくコミットできますね」と冷ややかに言われることもある。
人間の声が持つ吸引力は、確かに強力だ。特に若いときは、歌が入っていない音楽は、何かが足りない感じがしたり、お高くとまっているような気がしたものだ。
今でも、まず多くの人に自分の曲を知ってもらうためには、「歌」を突破口にしなければいけないのかなあという思いが断ち切れず、うじうじしている。
KAMUNAのファーストアルバムに入っている
『オルカのため息』という曲は、数年前にNHKのBS7『World Weather』のBGMとしてかなり長い間流れたこともあり、今でも覚えてくれていた人が、WEBでこのCDを見つけ、ポツポツと注文してきてくれる。この曲には英語の詞もついているので、次のアルバムにはヴォーカルバージョンをと思っているのだが、誰か歌ってくれないかな。いや、これに関しては、自分で歌うのは気恥ずかしいのではなく、単純に力量が足りないのだ。英語の発音も苦手だし。
できれば、「突破口」を開けるような人がいいなあ。理想は、女性なら石川セリさん。
誰か、仲介してくれないかしら。
あ、今回も最後は話が脱線してる……。ポリポリ。

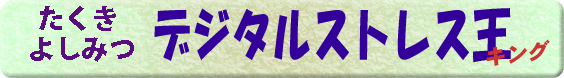


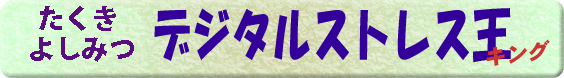

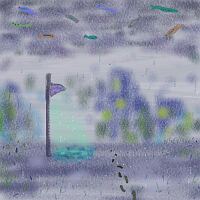

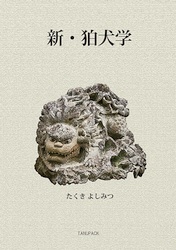
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)