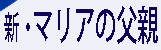2005年1月14日執筆 2005年1月18日掲載
お金の値段
このところ偽1万円札のニュースが毎日のように流れてくる。
スマトラ沖地震で十数万の人たちが命を落としている一方で、関西のおっちゃんがスキャナとプリンターでしこしこ作った、出来の悪い偽札のニュースが同じくらいの比重で報道されているのを見ると、どうにも不思議な気がする。
スマトラ沖地震のほうは、あまりにも桁違いの出来事で、被害を直接見聞きできない人間にとってはなかなかピンとこない。これは中越地震で自分の家を失ったとき実感した。それまでいかに、自分に直接降りかからなかった災害のニュースに無関心、無感動であったかを思い知らされた。
一方、パソコンで作った偽札のニュースは、もっと身近に感じられる。多くの人は「カラーコピーしただけの偽札なんて、通用するわけないよな」と思っている。でも頭の片隅では、「勢いで通用しちゃうこともあるのかな?」という想像もしているはず。
出来の悪い偽札も、初詣の雑踏の中で使えばばれにくいのでは? ……そんな発想も、恐らく複数の人間が同時期に抱いたに違いない。同類の事件が日本全国で次々に発覚しているが、同一組織が「偽札を初詣でごった返す神社やお寺で使え」という命令を全国的に発したとは考えにくい(一部、あったかもしれないが、それが「全部」ではあるまい)。要するに、この程度のことは「誰もが一度は考えたことがある」ことなのだ。
「誰もが一度は考えたことはあるが、やらないこと」を実際にやってしまうやつがいる。それだけで、ニュース性があるのだろう。
僕の未発表小説で『呪禁(じゅごん)』というのがある。400字原稿用紙換算(このデジタル時代に、もはやこういう数え方はどうかと思うのだが)で840枚の長編。ファイルの更新日付を見ると、1997年に書き上げたまま、発表できないままになっていることが分かる。
山北玄治(げんじ)というスリが主人公で、陰陽道などの要素を取り入れた現代の伝奇小説だった。(ああ、自分でも「だった」と過去形で書いてしまうところが哀しいわね)
そこに「500円玉偽造組織」の話が出てくる。
ずっと前から、紙幣の偽造は技術的に大変だが、硬貨の偽造なら簡単ではないか、という思いがあって、いつか小説の中で書いてみようと思っていた。
『呪禁』を書いた後、実際に偽500円玉事件が報じられて、自分の想像が正しかったことを知った。その前に小説が発表できていれば、もっときちんと満足?できたのだろうが……。
偽札事件報道を何度も見せられるうちに、ふと『呪禁』のことを思い出し、あのシーンがどんなだったのか確かめてみたくなった。
(……略……)
フロントでは、予想外の追加料金を請求された。
冷蔵庫の中のアルコール類をすべて飲んでしまったためだった。
「細かいんだが……」
少し言い訳口調で、玄治は五百円玉を数枚出す。
それでもポケットの中の財布はあまり軽くならない。
このところスリの成果が上がっているので、もう一つの「副業」のほうはさぼり気味だったのだ。
頭も身体も疲れている。こんな日は副業のほうに精を出そうと決めて、玄治は地下鉄に乗り、「事務所」へ向かった。
事務所は、大阪、阿倍野区の雑居ビルの中にある。
銀行とゲームセンターの間の路地を入ると、急に人通りが減る。二本向こう側の路地両脇にはラブホテル街が形成されているが、この路地は取りたてて店もなく、奥へ入るにしたがって寂れた感じになる。
路地に入って三軒目のビルには、飲み屋がいくつか入っている。その向かい側は野ざらしの駐車場。さらに奥へ進むと、おでん屋と、どうやって成り立っているのだろうと思うような小さな金物店。
「事務所」は、その路地のどん詰まり近く、薄汚れたモルタル塗りの三階建てのビルの中にある。
ビルの入り口は昼間から薄暗い。女性でなくとも、一人では怖くて入れないような雰囲気だ。
軋み音がひどくなったドアを押してロビーに入ると、さらに薄暗い通路が奥へ向かって延びている。通路には窓がないので、奥へ行くに従って暗くなる。もちろん天井に照明はあるのだが、ついていたためしがない。
その突き当たり右側に、引っ込んだ一角がある。三畳ほどのスペースで、奥には壊れた清涼飲料水の自動販売機がある。ショーケース部分のガラスにはひびが入り、鉄板にはあちこち錆が浮き出ている。もう何年も前から「故障中」という張り紙がコイン投入口をふさいでいる。
もっとも、その張り紙がなくても、こんな場所にあるボロ自販機に金を投入する者はいないだろう。
玄治は周囲を確かめ、自販機の裏側に手を入れた。
廃物のように見えるこの自販機には、実は高性能な電子施錠装置がつけられている。裏側にある、一見ただのボルトのように見える三つのスイッチを、特定の順番で押すことにより施錠が一時的に解除できる仕組みだ。
スイッチを押して施錠を解除すると、かすかな電子音がする。それを確かめてから、玄治は自販機の鍵穴に鍵を差し込む。この鍵は、裏側の電子施錠を外して初めて回すことができる。
表側ショーケース部分の扉を開くと、中には縦に九列の商品シリンダーがある。九列のシリンダーはさらに上下に区切られていて、全部で十八のブロックを構成している。
そのシリンダーの各々に、無地のボール紙に包まれた、厚さ三センチ弱、石鹸箱を一回り大きくしたような、ほぼ正方形のパッケージがびっしり積み上げられている。
玄治の担当である右から二列目の下の段には、ボール紙の包みが五つ入っていた。
周囲を見渡し、改めて誰もいないことを確認してから、玄治はその包みを素早く鞄の中に入れる。
玄治の鞄は手提げにも背嚢にもなるタイプのもので、一見コンパクトに見えるが、かなりの量が収納できる。
そのまま素早く自販機の扉を閉め、鍵を掛けると、警報装置は再び動き出す。
ずしりと重くなった鞄を背負って、階段を上る。
二階の西端に「佐藤」という表札が出た部屋がある。
表札はカムフラージュで、住んでいる者はいない。
ドアは二重ロックになっていて、内鍵を掛けると外からは開かない仕組みだ。
中から内鍵が掛けられているときは、ドアの端に小さくマークが表示されるのだが、うまい具合に誰もいないようだった。
重いドアを開ける。郵便受けの裏側は改造してあって、巨大な箱が据え付けてある。
玄治はこの部屋では「佐藤治」である。住所を必要とする場合、山北玄治はこの部屋の住所の「佐藤治」になる。
玄治宛に郵便物が届くことはまずないが、この部屋には「佐藤健一様」「佐藤事務所御中」「佐藤デザインルーム御中」「オフィス佐藤御中」「佐藤政夫様」など、何種類かの宛名で郵便物が届く。それぞれが別人のコードネームになっている。
一応自分宛の郵便物がないか確認してみたが、「佐藤事務所御中」という郵便物が一通あるだけだった。
この部屋を利用しているのは常時五、六人いるはずだが、誰も互いに名前も知らない。たまに通路ですれ違うことがあっても、相手の顔をじろじろ観察などしないのが暗黙の流儀になっている。
表札は「佐藤」と出ているだけなので、郵便配達は恐らく、佐藤という一家が住んでいて、家族の誰か、あるいは何人かがデザインオフィスをやっていると思っているだろう。
電話は一本引いてあるが、常に留守番電話状態になっていて「はい、佐藤です……」という女性のアナウンスが流れるようになっている。
最低限度の物の保管と郵便物管理だけのための部屋。
自分の他にどんな人間がここを利用しているのかは分からないし、知ろうとしないというのが掟になっている。
「結(ゆい)」と呼ばれる組織に関わっている人間たちだということだけは分かっているが、それ以上のことは詮索しない。
中は六畳一室だけで、事務机が二つ、ロッカータンスが三つ、コンテナが三つ置いてある。
狭い部屋の中は、細かくなわばりが分けられていて、自分のなわばり以外の物には一切手を触れてはならないことになっている。
玄治はトイレだけを使用できる。言い換えれば、トイレのドアを開けることができるのは玄治だけだ。
トイレのドアを開けると、壁際にはコートや上着が吊されている。つまりこのトイレは玄治専用のロッカーなのだった。
便座を開けると、中には丸い板が渡されていて、物入れのようになっている。玄治はそこに、今、下の自販機から取ってきたボール紙のパッケージを置いた。
そのうちの一つを開く。
中にはびっしりと五百円玉が詰まっている。
五百円玉というのは、直径が二十六・五ミリで、厚さは二ミリ。一枚の重さは七・二グラムある。
パッケージ一つには、これが四列に五十枚ずつ並んで入っている。これで十万円。重さは一・四キロ以上ある。五つもバッグに入れると七・二キロ。とんでもない重さになる。無論、この状態では歩き回れない。
小銭入れと呼ぶにはかなり大きな財布二つに、入れられるだけ入れ、残りはこうしてストックしておく。
玄治は持てるだけの五百円玉を持ち、すぐに部屋を出た。
玄治の「副業」は、この五百円玉を札に換えることだった。
この五百円玉が偽造のものであることは明白だ。「結」の元締めである「庄屋」が偽造している。
偽札と比べて、硬貨の偽造ははるかに易しい。問題は一つあたりの価値が低いから、偽造してもうまみがないということだ。一円玉に至っては、造幣局で大量生産してさえ原価のほうが高くつく。
一万円札なら、百万円がほんの一センチほどの札束にすぎないが、五百円玉で百万円といえば二千枚も必要になる。五百円玉二千枚は、十四・四キロある。これでは運ぶのも目立つし、大きな取引はまったくできない。
そこで、偽造した五百円玉は極力紙幣に換えていかなければならないが、一度に大量の換金作業をすれば目立ち、すぐに足がつく。継続的に五百円玉を偽造するためには、なるべく小規模に、目立たず、広範囲で換金していくことが必要になる。その作業をするのが「小作(こさく)」と呼ばれる、アウトローたちだ。玄治もそのひとりである。
「小作」は庄屋から支給された五百円玉を元手にして、庄屋に支給額の半額にあたる一万円札を戻す。
二百枚入りのパッケージ一つは十万円だから、パッケージ一つにつき、一万円札五枚を戻す。残り五万円が小作の稼ぎとなる。
無論、郵便局や銀行で両替するなどという安直な方法は厳禁だ。五百円玉だけの大量換金が何度も重なれば、当然怪しまれる。また、自動販売機を使って釣り銭をせしめるのも禁じられている。
小作に渡される偽五百円玉は極めて精巧なもので、まず本物と見分けがつかないが、一台の自販機から大量に見つかったとなれば厳密に調べられる恐れがある。
もし結で禁じている方法で小作が五百円玉を札に換えたことが分かれば、その時点で結から除名され、庄屋との取引は永久停止になる。いや、おそらく「取引停止」だけでは済まないだろう。最近は掟を破って消された小作の噂は聞かないが、結によって消されることくらいは容易に想像がつく。
小作たちは、競馬、競輪、パチンコなどで五百円硬貨をせっせと札に換えていく。普通、プロのギャンブラーの場合、投入額と回収額が同じだったら飯は食えないわけだが、小作たちは、同額回収でも投入額の半額の儲けが出ることになる。例えば、腕のいいパチプロにとって、これはそれほど厳しい条件ではない。
競馬でも、大勝ちしなくていいとなれば、おのずと安全策が取れる。
複勝で細かく「ころがし」をするという手もあるが、これは一度でも外すと振り出しに戻ってしまう。
玄治がよくやるのは「高入れ」という方法だ。外したレースの次は、必ず直前に負けたレース以上の金を投入していく。
例えば一万円投入したレースを外した場合、次のレースで配当二倍の馬に同じ一万円を投入したら、取れても差し引きはゼロにしかならない。一万円すったら、次のレースでは一万円以上取れるように、さらに高い金額を投入する。負けが続いても、絶対に投入金額を引き下げない。逆にどんどん高い金額を投入する。ただし、自信がないレースには決して手を出さない。
玄治は競馬のデータ収集に時間をかけるタイプではない。だから、出走数の多いメインレースや荒れやすい距離の長いレースには手を出さない。出走頭数が少なく、距離の短い、読みやすいレースにだけ賭けていく。
そうすれば、まず当たるレースが一レースはある。その時点でやめてしまえば、収支はマイナスにはならないわけだ。
普通の競馬ファンは多少の儲けでは満足できず、さらに手を出し墓穴を掘る。だが、小作にとっては、五百円玉を万札に逆両替することが最初から目的なのだから、大儲けする必要はない。とんとんでも投入金額の半額儲かるという精神的な余裕は大きい。
(……略……)
今読み返してみると、自分で書いた文章でありながら「へええ、そうなのかぁ」なんて感心しながら読んでしまう。もちろんこれは「小説」であり、すべて僕の妄想から成り立っている。「ころがし」「高入れ」などという裏社会用語風の言葉も、勝手に作ったものだから、予想屋のおっちゃんに言っても通じないのでご注意。
ただ、僕は今でも、こういう世界、つまり「絶対にばれない犯罪」を継続している社会は存在すると思っている。
いや、これは暴論、極論と思われるだろうが、「国際経済」とか「グローバルスタンダード」「基軸通貨」なんて言葉にも、これに近いトリックを感じてしまうのだ。
犯罪か否かを決めるのは、「力」なのだから。
……とまあ、このへんで一旦終わろう。
少し前、AICに短編小説をまるまるアップしたときはかなりのブーイングがあった。
「あんななげーの、読んでる時間ねえよ」
と。今回もここまでで十分長いので、一旦「締め」ます。はい。
以下は余力のあるかただけ読んでみてください。
(今読み返すと、いろいろ変なところもあるのだけれど、僕自身は、結構このシーン好きなのよね)
(……略……)
五百円玉逆両替は、玄治にとって、保険でもあり、日々の生活にバラエティを持たせるための手段でもあった。
玄治はこの五百円玉逆両替の小作を始めて二年になる。
仲介してくれたのは、行きつけの飲み屋でたまに顔を合わせる、通称「春さん」という初老の男だ。
小柄だがほどよく筋肉がつき、身のこなしも軽い。顔は歳の割にやや童顔で、見ようによっては女形でもできそうな愛らしさを秘めている。
春さんと知り合ったのはさらに三年ほど前に遡るが、信用を得るまでにそれだけの年月が必要だったということらしい。そこから推し量るに、ほとんど顔も合わせない他の小作たちも、かなり厳選されたメンツなのだろう。警察にやっかいになることがない、地道な裏稼業の人間たち。もしかしたら正業として他に立派な肩書きを持っている者もいるかもしれない。
玄治は今でも、春さんが最初に偽造五百円玉逆両替の仕事を持ちかけてきたときのことをよく覚えている。
阪神大震災の後、行きつけの飲み屋で久々に春さんと遭遇した。
春さんは酔っていて、いつもより饒舌だった。
「なあ玄治、今度の地震でどれだけの金がのうなったと思う?」
玄治は一瞬その言葉の意味が分からなかった。被害者の数は連日のように報道されていたが、「金が」という言葉はまだあまり聞かれなかった。
「経済的な損失という意味ですか? 復興にかかる金額?」
「あほ。そんなんやない。単純に燃えてしもうた札束ってことや。物やない、現金。箪笥貯金しとった金が燃えたはずやろ。結構な額になるんとちゃうか?」
「そうかもしれませんね」
「そやろ? したら、この日本という国に出回っとる現ナマが減ったいうことや。減った分は補充せなあかんわな。国は当然いつもより多めに新札を刷るやろ? そんとき、どんくらい増やして刷ったらええかちゅう計算式みたいなもんがあるはずやろ。これくらいの範囲で住宅と商店が燃えたら、これくらいの箪笥貯金が燃えたはずやという……」
「そんなもんですかね」
「あたりまえやろ。金作るほうかてプロやがな。行き当たりばったりで札びら印刷しとるわけやないで」
「かもしれませんね」
「ぼーっとしとったらあかんで。ここまで言うたら分かるやろ?」
「何がですか?」
「あほやな。そこまで言わせるんか? 逆に、増えた金もあるはずやろが」
「増えた金?」
「そうや。一人もんが貯め込んでた貯金とかや。一人もんが通帳と一緒に燃えてしもうたら、その金はもう誰も引き出せん。銀行の中で動かない金ゆうんは、要するに銀行のもんや」
玄治は春さんの正体を知らない。普段は通天閣あたりを根城にふらふらしているらしいが、郊外に大きな家を持っているのだという噂も聞いたことがある。
一体何をして暮らしているのか、不思議に思っていたが、引き替えに自分のことを説明することになるのは藪蛇なので、訊いたことはなかった。
「金って、考えてみたら不思議なものですよね。ただの記号みたいなものかもしれない」
玄治がそう呟いたのを、春さんは聞き逃さなかった。
「どうや。仕事せんか? 興味があったら、明日、訪ねてこいや」
そう言い残し、春さんは一足先に店を出ていった。
翌日、春さんに言われた場所を訪ねた。
指定された場所は通天閣そばにある芝居小屋だった。
大衆演劇をかける汚い常設小屋だが、その日は空いていた。このへんでは顔の春さんは、小屋の主とも仲がよく、空いている日はこの小屋に自由に出入りし、ときには寝泊まりもしているようだった。
照明器具を入れた汚い木箱の蓋の上に、春さんは五百円玉と五十円玉を一枚ずつ置いてこう言った。
「玄治よ、五百円は五十円の何倍や?」
春さんはこういう謎かけのような話し方を好んだ。またいつもの調子できたかと、玄治は苦笑しながら答えた。
「十倍ですね。俺の計算が間違っていなければ」
春さんはにやっと笑って言った。
「ちゃうわ。そんなにはならん。二倍や。わしはこの五百円玉と五十円玉の話をしとるんや。両方の手え出してみい」
玄治は素直に両手を出した。その右の掌の上に、春さんは出してあった五百円玉を、左手に五十円玉をのせると、懐から五十円玉をさらにもう一枚取り出して、玄治の左手の上にのせた。
「どうや。大体同じ重さやろ」
「なんだ。重さが何倍かという話ですか。つまらないなぞなぞだ」
「つまらんか? あかんなあ、そないなことでは。おかしいと思わへんか?」
「何がです?」
「五十円玉も五百円玉も、同じ白銅貨や。それなのに、五百円玉は五十円玉の二倍の重さしかあらへん」
「貨幣ってのはそういうもんでしょう。昔のように金や銀そのものの価値がコインの価値と同じだという時代じゃあるまいし。貨幣の価値は約束事で支えられているわけですからね」
「玄治よ、見損なったで。おまえはそういう常識から自由な場所で生きとると思うとったがなあ」
その言葉に玄治ははっとした。
その通りだった。
社会の約束事など信じることなく、野生動物のように自分だけを信じて生きてきたつもりだった。それが、いつしか固定観念にとらわれてしまっている。
「つまり……造幣局としては、五十円玉二枚分のコストで五百円玉を造っているということを言いたいわけですね?」
玄治の言葉に、春さんの顔がたちまちほころんだ。
「そういうことや。五十円玉かて、造幣局は原価割れで造っとるわけやない。ということは、五百円玉の原材料費は、どう考えても百円以下やいうことになるわな。これは韓国の五百ウォンや」
そう言うと、春さんはポケットからもう一枚のコインを出して、五百円玉、五十円玉の横に置いた。五百円玉そっくりなその硬貨が、よく自販機やゲーム機で不正使用されることを、もちろん玄治も知っていた。
「同じ材質で同じ大きさやけど、ウォンは円よりずっと安い」
「そうですね」
「世の中いうのはそういうインチキの上に成り立ってるんや。十万円記念銀貨いうのが造られたとき、材料になった銀の値段は三万円くらいのもんやった。残り七万円分は国の丸儲けや。五百円玉いうのはそれどころやない。しかも、札とちごうて、造るのは簡単や。金型とプレス機があれば造れる」
「それでも、大量に儲けるには利ざやが小さそうですね。初期設備投資を回収するには最低でも数千万円は儲けなければ馬鹿みたいだし、億の単位で儲けようとしたら、それこそ、とてつもない数を造らなくちゃならない」
「そういうことや。五百円玉で百万円分いうと、二千枚……重さにすると十五キロ近くある。一千万なら二万枚、一億なら二十万枚……一トン半や。そんな大量の五百円玉をいっぺんに両替したらすぐに足がつくわな。普通に買い物するいうても、五百円玉だけでできる買い物いうたらたかが知れとるわ。そこで小作人が必要になるんや」
「小作人?」
「どうや、玄治。小作にならへんか? おまえさんが堅気でないことはすぐに分かる。指先の器用さは並やないしな。パチプロの他にもいろいろしとるんやろうが、そこいらへんは訊かんことにする。ここから先の話は、裏の世界の者同士としてするんやで……」
……そうして玄治は小作になった。
庄屋の正体を探らないこと、他の小作たちのことも詮索しないこと、銀行や郵便局での両替は一切しないこと、自販機での一括大量両替もしないこと。むろん結の存在は口外しないことが条件だった。
(……略……)
//『呪禁(じゅごん)』(たくき よしみつ) 1997年執筆・未発表 より //


●おお、雪だ!
(c) Takuki Y. http://takuki.com
 デジタルストレス王・目次へ
デジタルストレス王・目次へ
 次のコラムへ
次のコラムへ
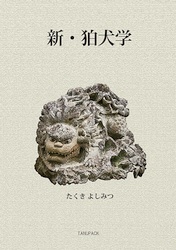
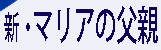


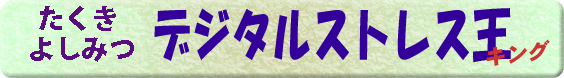


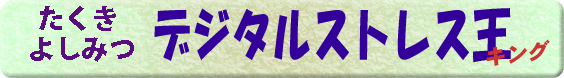



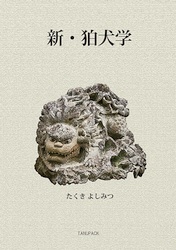
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)