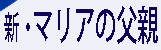昨日、
beの土曜版に連載中の「ソフ得!」の担当記者に、サイレントチェロを譲った。チェロマスター、ついに断念。
作曲をしたいのだから、楽器を弾けるようになるための修練に費やす時間と努力を、作曲作業に投入すべきではないか、というのが、断念の主たる理由。
37歳でもう一度ギターをゼロから練習し始めたときの経験から、どのくらい練習するとどのくらいうまくなるかは予測がつく。あのときの練習を50歳になった今、もう一度やるのは難しいとは、当初から思っていたのだが、やはり断念か……。
まあ、ほとんどの人はこうして言い訳を考えて、やりたいこと(いわゆる「夢」というやつ)をひとつひとつ諦めていくのだけれど……。
で、サイレントチェロを引き渡すとき、その担当記者(直接会ったのは2回目)と話をしていて、小説というものにはもう未来はないのではないか、という話題になった。
「今は漫画でしょう。あとは実用書」
これはもう、だいぶ前から言われていることだが、言われ始めたときより今のほうが、諦めの気持ちが重くのしかかる。
考えてみると、文章というものは、読解して、その意味を頭の中に再現しなければ情報伝達が完了しない。
音楽は音が耳に飛び込んできた時点ですぐ反応できるから、鑑賞する側は、ある程度受け身でかまわない。でも、小説は読者が意識して「読むぞ」と取り組まなければ始まらない。
漫画は画像を伴っているので、文字だけの作品より入っていきやすい。ましてやテレビドラマや映画などは、映像だけでなく音も伴っている。そういう形に直してやらなければ、「おはなし」を娯楽として伝達することは難しくなってきているわけだ。
中学か高校か忘れたが、国語の教科書に夏目漱石の『こころ』が載っていた。
『こころ』は哲学的なテーマを内包する作品である。今でも覚えているのは、作中登場人物の「先生」の心の闇に迫ろうとする「私」とのやりとりの途中、奥の部屋で針仕事か何かをしていた「奥さん」が、何気なく先生を制するというシーン。
「じゃ奥さんも信用なさらないんですか」と先生に聞いた。
先生は少し不安な顔をした。そうして直接の答えを避けた。
「私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用できないから、人も信用できないようになっているのです。自分を呪うよりほかに仕方がないのです」
「そうむずかしく考えれば、誰だって確かなものはないでしょう」
「いや考えたんじゃない。やったんです。やった後で驚いたんです。そうして非常に怖くなったんです」
私はもう少し先まで同じ道を辿って行きたかった。すると襖の陰で「あなた、あなた」という奥さんの声が二度聞こえた。先生は二度目に「何だい」といった。奥さんは「ちょっと」と先生を次の間へ呼んだ。二人の間にどんな用事が起ったのか、私には解らなかった。それを想像する余裕を与えないほど早く先生はまた座敷へ帰って来た。
「とにかくあまり私を信用してはいけませんよ。今に後悔するから。そうして自分が欺かれた返報に、残酷な復讐をするようになるものだから」
このシーンを、担当の国語教師・臼井先生は、僕ら生徒たちに挑戦するような笑みを浮かべて解説したものだ。
「分かるか? この奥さん、相当なタマだぞ。このタイミングでさりげなく『あなた、あなた』と呼ぶっていうところ、見逃したらだめだぞ。小説ってのは、こういうところをしっかり読まなきゃいかん。しかも、その裏で何があったのかくどくど説明しないところが漱石の文豪たる所以だな。分かるか?」
文学とはそういうものなのか、と、臼井先生の講釈を聴いていたのは35年くらい前のこと。
臼井先生にとって、漱石作品は知的な冒険ができる娯楽だったかもしれない。でも、僕にとって『こころ』は娯楽ではなく、国語という教科の教材であり、試験でいい点を取るために読まなければならない試練だった。
しかし、
『こころ』はもともと、朝日新聞の連載小説だったのである。
「かつては夏目小説の作品が新聞小説で、それを多くの国民が娯楽として読んでいたわけですよね。今はもう、そういう時代とは全然違いますから」
朝日新聞記者であった夏目漱石のずっと後輩にあたる、「ソフ得!」の担当記者が言った。
確かにそうだ。
35年前、すでに漱石の作品は娯楽ではなく、教材になっていた。そして今では「歴史資料」に近くなっているかもしれない。
漱石までさかのぼらなくてもいい。村上春樹の『ノルウェイの森』が今出たら、当時ほどのベストセラーになるだろうか。
多くの人が、文字情報を娯楽だとは思わなくなった。あるいは、文字情報だけで楽しむ想像力を持たなくなった。
……そういうことだろう。
考えてみると、オタマジャクシが並んだだけの譜面を見て「すばらしい音楽だ!」と感動できる人は極めて少ない。数十億の現存人類の中でも、ほとんどいないかもしれない。
CDが100万枚売れる曲の譜面を店に並べても、買う人は数えるほどだろう。
小説は、音楽作品における譜面と同じなのだろうか。つまり、「作品」ではあっても、鑑賞する対象ではない、とみなされつつあるのだろうか。
そうであれば、小説は、漫画やドラマの原作としてしか意味がなくなり、漫画家や映画制作者といった特殊な職業の人たちだけが読むものになりかねない。
そんなことは絶対にありえない! と、今、これを読んでいる多くのかたがたは反発を感じていることだろう。でも、実際、そうなってきているのだ。
ギターをもう一度練習し始めたのも、チェロをやろうと思ったのも、自分の作品が譜面のままでは誰も聴いてくれないからだ。こういう作品なんですよ、と、音にしてやる必要がある。そのための技術習得、という面が強かった。自分で音を出せると楽しい、といった動機からではない。
僕にとっては、楽器演奏は自分でやるより人がやってくれたほうがはるかに楽しい。自分の曲を自分で演奏するより、うまい演奏家が演奏してくれたほうが、ずっとずっと幸せになれる。そういう状況を作りだすための手段としての自演なのだ。
おはなしを作るという作業においても、僕は小説という形がいちばん好きで、自分で漫画や映画を作ろうと思ったことは一度もない。なぜなら、小説という「文字だけの表現手段」にこそ、人間の想像力を刺激する無限の力を感じるからだ。
夏目漱石の作品を、書店で買おうと思っても難しい時代になってしまった。そのうち、
過去の文豪と呼ばれる作家たちの作品も、PDFファイルで読まなければならない時代が来るかもしれない。
今また、絶版になった自分の作品を、少しずつPDF化して、
文藝ネットに掲載していくことを考え始めている。PDFって、嫌いなんだけれど、他に有効な手段が思い浮かばないから。
しかし、テキストファイルとして残っているのはせいぜい1996年くらいからで、それも本になる前の校正作業を経ていない未完成なものばかり。それ以前の作品に至っては、ファイルはおろか、原稿も残っていないかもしれない。
先日も、第四回小説新潮新人賞の候補作になった『ざ・びゃいぶる』という短編を読みたいというリクエストがあったのだが、探しても、原稿が見つからなかった。
絶版になった作品でファイルが残っていないものは、本から再入力するだけの気力はないし、ましてや未発表作品で手書き原稿さえ残っていないとなれば、PDF化もなにもない。
小説の命は、普段思っているよりもずっとはかないものなのだなあ。

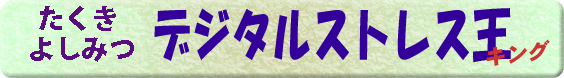


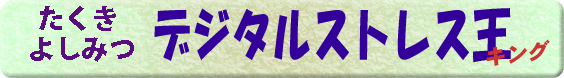



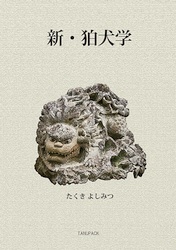
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)