考えてみると、自らを「デジタルストレス王」と名乗る今の重苦しい状況は、すでにあのとき予感していたことだった。
僕が初めて自分のパソコンを手にしたのは今から10年ほど前だっただろうか。正確な時期は覚えていないが、最初に買ったパソコンのことはよく覚えている。
IBMのPSV-VisionというCRT一体型モデルで、CPUはIBM 486SLC(バスクロック50Mhz。コプロセッサなし。486の前の386というCPUにアクセラレータのようなもの?をつけて、無理矢理486の名前を冠したようなCPUだったらしい)。ハードディスクは170MB。メモリーは8MB(後に追加したけれど、16MBが上限)、OSはWindows3.1(ああ、懐かしい)という代物だった。
ハードディスクが170MBというのだから、今のOSやアプリケーションは動かない以前にインストールさえできない。
それでも当時の人気モデルで、値段は30万円台だった。
実は、パソコンを買うまで、なかなかふんぎりがつかなかった。
パソコンかぁ……必要なものかもしれないけれど、面倒くさいなあ……というのが正直な気持ちだった。
当時、サンヨーのSWP-700というワープロ専用機で原稿を書いていたのだが、ようやく慣れ親しんだ執筆環境が変わることに抵抗があった。
加えて、一足先にパソコン(NECのPC9821)を購入して使っていた妻の様子を見るにつけ、パソコンとはストレスをもたらす悪魔の機械ではないかという疑念を抱いていたからだ。そして、結果はまさにその通りだった!
PS-V Visionはいきなりトラブル続きだった。
6万円近い大枚をはたいて購入したDOS-V(ああ、この言葉も懐かしい!)版一太郎Ver.5は、インストールした途端にOSが起動さえしなくなり、その後しばらくは放置されていた。
後で分かったことだが、インストーラがCONFIG.SYSを勝手に書き換えてしまうため、Windowsマシンとして設計されていたPS-V Visionでは、Windowsが起動しなくなるのも当然なのだった。
後日、OSの再インストールをして(当時はOSがCD-ROMではなくフロッピーディスクでついてきたので、この作業だけで半日はつぶれた)からも、仕事にはなかなか使えなかった。DOS-V版一太郎を諦めて、Windows3.1版一太郎をインストールしたが、これも思うようにサクサク動いてくれず、パソコンを買ったというのに、小説だけはワープロ専用機で書いていた時期もあった。
原稿を書くのにワープロソフトを使っていることが間違いなのだと気づき、テキストエディタ秀丸を使うようになるのはその後1年以上経ってから。縦書きのできるQXエディタの存在に気づいたのはさらに後のことだ。
まあ、この頃の苦労は無駄にはなっていない。おかげでパソコン雑誌に連載を持ち、1997年には『鉛筆代わりのパソコン術』という本まで執筆してしまったのだから。
インターネットには、パソコン購入以上に抵抗感があったが、結局これも今ではビジネスにまでしているのだから、なんだかなあ……。
コンピュータとインターネットに依存しなければ作家活動も続けられなくなったことは大変な不幸だが、デジタル世界に飛び込まなければ、今頃のたれ死にしていたかもしれないことを思えば、仕方のない選択だったと思う。
パソコンを使うようになってから、日々のストレスは著しく増大したが、中には楽しいこともあった。
パソコン購入後、最初に感動したソフトは、実用的なものではなかった。
「TK花火」といい、いわゆる環境映像ソフト(スクリーンセーバー版もあり)なのだが、その美しさに思わず見とれてしまった。
Readmeを読み、作者の川和利匡さんにファンメールを送った。
「僕は音楽をやっているんでスタジオ機材を一通り持ってます。今度、花火の生音をDATで録音してくるから、このTK花火用データも作ってみますね」と書き添えた。
花火用の生音データは約束通りすぐに作成し、川和さんに送った後、ニフティのウィンドウズフォーラムに公開した。プログラムではなく単なるデータだが、僕の「フリーソフト作家デビュー作」である。
それ以来、川和さんとはメールのやりとりをするようになった。プロのプログラマーなので、あまりくだらないことで煩わせるのは気が引けたが、パソコンでトラブルに見舞われたとき、相談するにはいちばん頼りになる人だった。何度助けてもらったか分からない。
例えば、ワープロ専用機で作成した文書ファイルをテキストファイルに変換すると、改行コードで整形されてしまう機種がある。入力したときの画面表示文字数で、強制改行整形されてしまうのだ。
この「改行コードで整形」というのは、メール文書などでは、返信のとき、引用符が行頭にきれいにつくため好都合だが、一般の文書では、再編集するときの障害になる。
しかし、改行コードを機械的に外してしまうと、「本来の改行」も消えてしまい、ベタッとつながったとんでもない文章になってしまう。
意図した「本来の改行」は残し、整形用に入っている改行コードだけを取る方法はないものかと相談したところ、翌日、簡単なプログラムが添付ファイルで送られてきた。
実行してみると、数百枚の原稿が、瞬時にして改行整形の取れた原稿に変換される。
劇的な効果に感動し、「これはぜひ一般公開しましょう。僕と同じように改行コード削除で悩んでいる人はたくさんいるはずですから」と進言した。
すると「お任せします。タヌパックのフリーソフトということで、適当に公開してくれていいです」という返事がきた。
これがフリーソフト「取れたぬ君」誕生のいきさつだ。
おかげで、タヌパックのフリーソフトは「TK花火用生音データ」と「取れたぬ君」の二本立てになった。
当時すでに、オンラインソフトをCD-ROMに収録して売っている書籍や雑誌がたくさんあった。今のように通信速度が速くない時代だったから、こうしたCD-ROMはユーザーにとってはありがたかった。
ベクターはオンラインソフト配布に関しては草分け的なベンチャー企業で、「PACK○○」という、巨大なオンラインソフト集を販売していた。(○○には2000とか5000とか、収録したソフトの数を示す概数が入る)
「PACK」に収録したソフトの作者には無料で「PACK」を送ってきた。「PACK」は年々収録ソフト数が増えて豪華になり、最後は1万本を超すソフトを収録した十数枚組の分厚い箱詰めパックになっていた。
インプレスは、フリーソフト集に収録したソフトの作家たちを東京の料亭に招いて慰労会を開いてくれたことがある。地方在住のソフト作家には、交通費と宿まで用意してくれた。
「TK花火用生音データ」も収録されていたので、僕にも招待状が来た。
どんな慰労会なのか興味があり、図々しくも一度参加してみた。(これも川和さんのおかげだ。)
新宿副都心の高層ビルの中にある日本料理屋に、数十人のフリーソフト作家たちが集まったのは、なんとも不思議な光景だった。
やはり、みなさん若く、理系の顔?が多い。
僕の正面に座っていたのが
画像ローダーSusieの作者・たけちん氏。僕はそのときSusieを知らず「
GVみたいなもんですか?」なんて訊いたのを覚えている(失礼しました!)。
今ではGVよりSusieのほうが有名になっているし、特に「プラグイン」(本体に追加して使う補助プログラム。それだけでは動かない)で機能が拡張できるという方法は、他の多くのフリーソフトに影響を与えた。
Susieのプラグインは、たけちん氏以外にも開発している人がいる。また、Susieプラグインを利用できる他の画像関連ソフトも、その後数多く出現した(
ViXや
Linerが有名)。
たけちん氏は見るからに真面目そうな好青年で、強く印象に残っている。気負いもてらいもない。散会後、一緒に新宿駅まで歩いて帰ったのだが、終始、さわやかというか、自然体を崩さない。
俺が俺が、という自己顕示欲の集団のような芸能界をかいま見てきた僕には、一種のカルチャーショックというか、こういう人たちがフリーソフトの世界を築いているんだなあと、妙に感心したものだ。
ソフトの著作権や、著作権ビジネスのことを考えるとき、どうしてもフリーソフト作者たちのことを思い浮かべてしまう。自分もまた、創作の現場にいる人間として、彼らの精神に恥じない行動をしていかなければ、と思う。
インターネットがここまで発展したのは、ビジネスとしてだけではなく、根幹に「知識や技術を広く無償で共有する」という精神があったからこそだ。
もしも、巨大資本の力「だけ」がデジタル世界を操れるとしたら?
想像してみてほしい。一歩間違えば怖ろしい独裁社会、あるいは低俗なだけのゴミ溜めになっているかもしれない。
ソフトビジネスはこれからの経済を支えていく重要なものであることは間違いない。もちろん、努力や苦労は正当に金銭的な報酬という形で報われるべきだ。
しかし、巨大企業が市場を独占していく状況下では、独創的で魅力的なソフトは出にくくなるということもまた、多くの人が感じていることではないだろうか。
コンピュータソフトだけではなく、音楽や文芸など、広い範囲でそれは言える。
本が売れないのは、ブックオフや図書館のせいばかりではない。本そのものの魅力が乏しくなっているから……言い換えれば魅力的な本が出てこなくなったからではないのか。
記憶に残る魅力的なメロディーが出てこなくなり、大人たちが過去の音楽しか聴く気がしなくなってしまったのは、音楽産業が文化の創造という志を忘れ、ターゲットを子供たちに絞って百万枚売れる音楽だけを追いかけ続けてきた結果ではないのか。
そう考えていくと、企業の論理に左右されず、自分の信ずるものを自分の力と責任で世に問うという「フリーソフトという思想」こそ、デジタル世界の救いかもしれない。
問題は、そのフリーソフトの精神とソフト産業の営利活動が、これから先どのように両立し、互いに磨かれていくか、ということだろう。

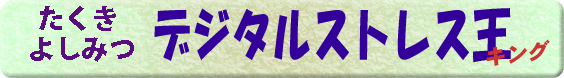


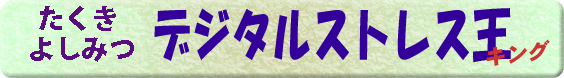



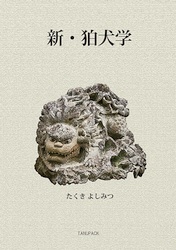
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)