9月前半はずっと、
KAMUNA6年ぶりの新作CD
『Orca's Song -KAMUNA 3-』のマスタリング作業やジャケット制作などにかかりきりになっていた。
マスタリングというのは、マスターテープ(今は最終形がテープではなくディスクであることも多い)の音を、CDに収録する最後の形にまとめる作業のことだ。
例えば、今まで、タヌパックスタジオで制作した音楽のマスターテープはDAT(サンプリング周波数48kHz)だった。音楽CDのサンプリング周波数は44.1kHzだから、マスタリングには、周波数変換という工程も含まれる。
また、CDに収める際、全体の音量をギリギリまで上げるという作業をすることもある。クラシック音楽など、ダイナミックレンジが広い音楽では、フォルテシモ部分をピークレベルに合わせると、ピアニシモ部分がほとんど聞こえない。高級オーディオで鑑賞する場合はそれでいいのだが、最近は、携帯CDプレイヤー&イアフォンでしか聴かないとか、もっぱらカーオーディオでしか音楽を聴かないという人も増えているので、ポップス系の音楽では、必ずと言っていいほど、最後にはリミッターやエンハンサーを駆使して平均音量レベルを高く確保する。これをやると最大音量と最小音量の差が縮まり、「でかい音で一見迫力があるようだけど、全体に一本調子でのっぺりした音楽」になる。僕はあまり好きではないけれど、やはり最終的にはできるだけ平均音量を上げてマスタリングする。そうしないと他の市販音楽CDと差ができてしまい、ラジオの放送などの際、不利になるし、平均音量の大きなCDに慣れたリスナーたちには、素人臭く聞こえてしまうだろうからだ。
マスタリング作業をしていて気がつくのは、最初からデジタルで録音するようになった現代の録音現場では、アナログ時代の録音技術や勘がそのまま通用しないということだ。
アナログ録音の時代は、超低音や超高音はレベルが自然に減衰した。低音などは、どうやって豊かに響かせるかで苦労したものだが、デジタル録音では、超低音も超高音もすべてそのままのレベルで録音されるため、ベースなどは逆に低域をカットしないとほとんど使えない。スピーカーから再生されないような超低音が録音され、音割れや不透明感が生じてしまうのだ。
ウッドベースなどは、低音を拾うのに苦労するのではなく、いかに低音をカットするかで苦労する。思いきってローカットフィルターをかけたりしないと、ベースらしく聞こえない。
そんなこんなで、マスタリングの途中でどうしても細かな部分が気になり始め、ミックスダウンの時点まで戻ってやり直す……ということの繰り返しだった。
どんなにいい曲でも(自画自賛)、何十回、何百回と繰り返して聴いていたら嫌になる。
もっとも、アナログ録音時代のほうが情緒があってよかったからといって、デジタルからアナログに戻ろうという気にはなれない。あらゆる点でデジタルのほうが作業が格段に楽だからだ。特にコンピュータを使ったオートミックスなどは、その便利さを一度知ってしまったら、二度と手動の作業には戻れない。
録音機材の値段もまったく違う。アナログ録音の時代には、プロレベルの録音を自宅でできるなどということは到底考えられなかった。
音楽の本質は、音質ではない。よいメロディー、豊かなオリジナリティ。それが記録できていればいいじゃないか、という割り切りがないと、作業は進まない。
ところで、KAMUNAはギターデュオだから、当然ギターが主役なのだが、CDの制作では、いつもベースやキーボードというサポート楽器のクオリティで悩む。
四畳半の部屋にグランドピアノは置けないし、生ピアノを録音するための設備投資もできないから、キーボード類は全部サンプリング音源になる。ベースはベーシストを呼べばいいのだが、ブライアン・ブロンバーグやエイブラハム・ラボリエル並みのぶっとぶような腕のベーシストは周囲には少なく、また、いても、ギャラが払えなかったり、頼むのが面倒だったりする(ああ、情けない)。
いろいろ試行錯誤しているうちに、一部は自分で弾き、あとは本物のベースを長めにサンプリングした特製の音源でMIDI再生するというスタイルが定着した。MIDIを使うが、MIDI臭く聞こえさせないように苦労する。でも「なんだ、一見それらしいけど、やっぱりMIDIじゃん」とばれてしまうと、とっても貧乏くさいので、どこまで凝るか、すごく悩む。
基本的には、MIDIはMIDIで割り切った使い方をしたほうがかっこいい。パーカッション類ではそっちの方向でやっている。
ミュージシャンには、ところんアナログのクオリティにこだわるタイプと、音楽性が豊かに表現できれば手段にはこだわらないタイプとがいる。
KAMUNAのステージや録音を手伝ってもらっているキーボーディストの堺敦生氏は後者で、「実」の部分にはとことんこだわるが、細かな音質や質感にはさほどこだわらない。
ライブの会場に行っても、備え付けのグランドピアノをパラパラっと弾き、「う~ん、これならキーボード持ち込んじゃったほうがむしろクオリティ高いかもしれませんねぇ」なんて言って、自分のキーボードに入っているサンプリングのピアノ音源を使う。サンプリングのピアノは、ピアノとは似て非なるものと断言するピアニストがたくさんいる。彼は生ピアノの仕事のほうが得意らしいが、ピアニストとしてはかなり変わり種かもしれない。
僕も同じタイプで、MIDIで代用できるならそれでいいじゃないの、という考え方だ。
もちろん、腕のいいミュージシャンが生でやるのがいちばんいいに決まっているのだが、それが無理ならば、センスのないミュージシャンとやるよりはMIDIを使ったほうがいいと思ってしまう。
MIDIは嫌いだが、本当に便利。そこが哀しい。
よく、歴史に残る芸術家たちが現代に生きていたら、自分の創作にコンピュータを使うだろうか、という話が出る。
ベートーベンは「魂の人」だから、絶対にMIDIなんか拒否して、全部生でやるだろう、と言う人もいれば、いや、耳が聞こえなくなってからは、MIDIを武器にコンピュータ音楽に没頭したかもしれないと言う人もいる。
イメージからして、モーツァルトはもっともコンピュータ好きに見える。固定観念にとらわれず、新しい楽器が出ればすぐに試してみたんじゃないだろうか。
「サリエリさん、あんたにはこの自由な世界が分からないだろうね」なんて言いながら。
でも、天才であるがゆえに、その時期を経て、今のようなデジタル漬けの時代に入った後は、一転して、敢然とアナログだけの音楽を追求しているような気もする。
「あんなのは子供の玩具だよ。ボクはもう飽きたね」なんて言って。
美術界では、ダリやマグリット、あるいはアンディ・ウォーホールなどは一見デジタル好きに見えるが、彼らがコンピュータを使い始めたら、むしろ自らの存在価値を脅かす結果になるかもしれない。
レオナルド・ダ・ヴィンチは、コンピュータがある現代に生まれていたら、そもそも絵を描いていなかったかもしれない。プログラマーや建築家、あるいは先端科学者などになっていた気がする。
一方、棟方志功やゴッホ、円空などは、最もコンピュータが似合わない美術家だろう。現代に生きていても、生き方や創作方法はまったく変わらないに違いない。
やはり、音楽(空気の振動)とは違って、美術は作品が「物質」であるだけに、アナログの世界を死守しないといけない運命にありそうだ。
アナログ技術がピークを迎えた時代に人生前半を終え、デジタル技術全盛の現代に年老いていく僕は、はたして幸せなのだろうか?
マスタリングやジャケットの制作で四苦八苦しているとき、本当はこの作業は他の人がやるものなのに……と、ついつい思って辛くなる。全然楽しくない。
でも、一人でもその気になればできる「手段」が、デジタルという形で与えられていることは、やはり幸せなことに違いない。アナログ時代に果たせなかったことを、デジタル時代にしつこく追いかけることができる。
デジタル技術がなければ、僕はとうの昔に音楽活動を諦めていたかもしれないのだから。

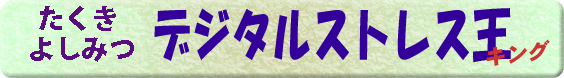


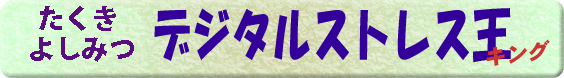

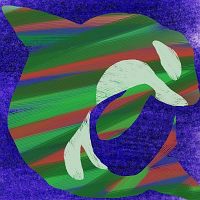

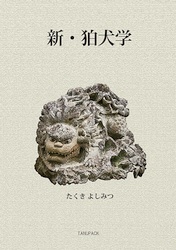
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)
