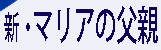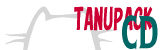2009年4月1日、朝日新聞全国版朝刊の1面と2面に、エイプリルフールかと見まごうような記事が掲載された。
「エコウォーズ 新エネの壁」と題された特集だが、第1回の風力発電に対する記述は、「風力発電は導入すべきものである」という先入観と偏見に満ちている。
ようやく日本にも少しずつ芽生え始めていた「エコの名を借りた税金の無駄遣いとエネルギー浪費を見直そう」という気運を、日本を代表するメディアが吹き消そうとするとは、とても残念だ。
風が不安定で、山岳地が多く、人口密度の高い島国日本という、風力発電には向いていない立地条件を無視して、「風力発電導入は必須」という結論だけが先行した論調は、あまりにも拙すぎる。
日本で風力発電が使い物にならないのは、改善してどうこうできるようなことではない。根本的に成立し得ないものなのに、無理矢理、税金を投入し、優遇措置を法律で決めてしまったために、問題がここまで大きくなってしまったのだ。
電力線の整備も蓄電池も、莫大な量の石油を投入して作られる。送電線整備はともかく、大規模蓄電池は耐用年数や廃棄の問題もある。巨大風車の耐用年数はわずか17年である。17年後の撤去費用を誰が持つのかも決めないまま、強引に建設し続けてきている。
エネルギー問題の基本は、得られるエネルギーがいくらかではなく、それに対して投入したエネルギーを正確に把握することである。巨大風車を設置して、どれだけの化石エネルギーが節約できるのかという数値を示せないまま、「風力発電は新エネルギーの主役だ」「安くて大規模な発電ができる」といったフレーズを書き連ねる。これでは、読者の目はますます曇ってしまう。
風力発電は、地熱や水力と違って、人間の都合で発電量をコントロールできない。風が一定してふかない日本では、これは致命的な問題だ。
この決定的な欠点を無視して、総発電量やプラントの潜在発電能力(最適な風が吹いたときの最大出力にすぎない)の数字を並べたてるのはやめていただきたい。
取材源も、関連企業、誘致した自治体の首長らで作る「風力発電推進市町村全国協議会」、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)、経産省元幹部など、推進したい側のコメントが切々と書かれ、現場である電事連の技術部長のコメントなどは、あたかも悪者の言い訳のように書かれる。
お偉いさんの言葉ではなく、もっと現場の生の声を拾ってほしい。電力会社の現役社員が口を閉ざしているなら、元社員でもいい。電力配給調整の現場をよく知っている人に取材すべきである。彼らは、風力発電の電気がいかに迷惑かをよく知っているはずだ。
もちろん、巨大風車を設置されてしまった土地で何が起きているのか、住民の生の声もしっかり聴いてほしい。
「政治的な決断さえあれば取り除ける障壁も多い」というが、それこそが大問題だ。
国策として、事業が成立しないことを承知の上で補助金(つまり我々が払っている税金)を投入し、まともな競争や試験を経ずに事業をごり押ししてきた。その結果、環境を破壊し、住民の健康を奪い、電力会社からは迷惑がられる巨大風車が、もともと無理な場所にこれだけ建てられてしまった。普通に競争させていれば、まともなものは生き残り、だめなものは生き残らない。
「電力会社の買い取り価格が低すぎる」などという日本風力発電協会のコメントをそのまま掲載しているが、とんでもないことだ。電力会社は、理不尽に高い価格で「いらない電力」を買わされているではないか。なぜそんな単純な事実さえも歪曲してしまうのか。
現代の石油文明社会においては、コストというのは石油消費量に比例している。コストがかかるということは、それだけ石油を使っているということなのだ。日本の風力発電がコスト的に成り立たないのは物理的、潜在的な宿命であり、それを税金投入で無理矢理推し進めたら、ますますエネルギーは浪費されていく。これはもう、とうの昔からまともな物理学者、経済学者たちが指摘し続けてきたことだ。その根本的な問題に一切触れず、未だに「もっと補助金をつければ」とか「法律で優遇すれば」という方向に話を持っていくのは論外である。
さらには、人類がこれまで経験したことのない羽根の直径が100mもあるような巨大風車を日本の山に並べて、どういう問題が起きるのか、現に起きているのか、なにも解説していない。
日本における風力発電は、全発電量の0.26%(2007年度)だという。これを工夫次第で10%や20%というレベルに引き上げられると、本気で思っているのだろうか。国土を荒廃させ、風車の周辺に住む人や動物の健康を奪いながら、無理に無理を重ねて4倍にしたとしても、ようやく1%なのだ。
根本的に無理だからこういう数字になるのであって、これは送電線網を再構築して解決できるような問題ではない。そんなもののために、巨額の税金を投入することが許されていいはずがないではないか。
日本に巨大風車を持ち込むことは、エネルギー政策でもなんでもない。税金を使い、石油の無駄遣いをして、一部の企業や人間に利権を与えているだけだ。
メディアがミスリードして、貴重な税金と石油エネルギーが使われた例としては、ダイオキシン汚染報道による「ダイオキシン法」制定と、全国への大型高性能焼却炉導入がある。後に、心ある学者たちが、「ゴミ消却によって出るダイオキシンは、環境中のダイオキシン総量においては無視できるような量であり、そもそもダイオキシンが猛毒物質であるという確実な根拠もない」と告発したときには、すでに兆単位の金が使われた後だった。これによって儲けたのは焼却炉メーカーと商社、そして事業を推進した関連団体に天下った官僚たちだった。
風力発電事業もこうした構図だが、背景に、二酸化炭素による地球温暖化という史上稀に見る世界的な情報コントロールがあるので、事実を知らせることが極めて困難になっている。
大型高性能焼却炉は、少なくともその後、まともに稼働している分、単純に粗大ゴミを押しつけたわけではないが、巨大風車はタチの悪い粗大ゴミだ。20年後、日本のあちこちに、撤去もされず放置された風車の残骸がたくさん見られるようになるだろう。それまでに、どれだけの自然が破壊され、どれだけの人と動物が健康と命を奪われるのだろうか。
「日本も低炭素社会を本気で目指すのであれば、多くの新しい政策が必要だ」というが、これほど危険な考え方はない。「低炭素社会」などというスローガンから生まれた二酸化炭素排出権売買という詐欺により、日本は欧米諸国から食い物にされようとしている。
人間が何をしたところで、世界の炭素総量は変わらない。質量保存の法則があるのだから。
完全にクリーンなエネルギー事業などというものはない。エントロピー増大の法則があるのだから。
何度でも繰り返すが、
大切なのは、限りある化石資源をこれ以上無駄遣いしないこと。生命の営みを実現している地球の循環環境を壊さないこと。それに尽きる。
今、自然の摂理を無視して日本に巨大風車を建てていることは、限りある石油を無駄に使っている行為に他ならない。本当に石油がなくなってきたら、こんな馬鹿げたことをしている余裕はない。最後の悪あがき、悪ふざけといえよう。
風力発電が使い物にならないのは根本的な問題があるからだ。国が「主要産業界への配慮」をしているからではない。
「そうした変化は政治の意思がなければ進まない」というが、「政治の意思」が、嘘に嘘を重ねて無理を推し通した歴史を振り返ってほしい。
昨今の似非エコロジープロパガンダは、太平洋戦争前の状況によく似ている。
日本は資源がない。大東亜共栄圏を実現し、閉塞状況を突破せねばならない……。
無理を国策で強行するというのは、国が破壊されることを意味する。
「エコウォーズ」とはよく言ってくれた。エコを大義として無益な戦争を仕掛けようとしているということか。エコウォーズによって殺されるものたちの声は、メディアに届くのだろうか。
無益な戦争を煽動していくメディアの責任は重い。
風力発電被害に関するミニリンク集
ο
ノーウィンドファーム・ネット  こちら
こちら
ο
南伊豆に今何が起こっているのか? ~ 渥美半島の風車被害から学ぶこと~  こちら
TOPページ「風力発電問題 南豆の和」
こちら
TOPページ「風力発電問題 南豆の和」  こちら
こちら
ο
風車病とは?  こちら TOPページ 黙殺の音 低周波音
こちら TOPページ 黙殺の音 低周波音  こちら
こちら
ο
伊豆熱川(天目地区)風力発電連絡協議会のブログ  こちら
こちら
ο
段が峰の自然(段ヶ峰の風力発電を考える朝来市民の会)  こちら
οブログ 弁護士の法的独白「風力発電の電気購入について」
こちら
οブログ 弁護士の法的独白「風力発電の電気購入について」  こちら
こちら
ο
ブログ”黙殺の音” 低周波音  こちら
こちら
ο
朝日新聞の記事「風車新設各地で反対 周辺住民へ説明不可欠」(編集委員・武田剛)  こちら
こちら

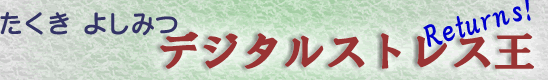


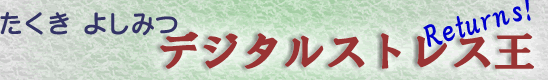

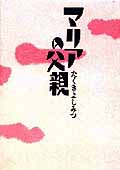
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)