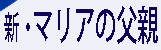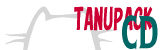静岡新聞が、2009年7月24日の紙面で「風力発電7カ月停止中、補修に障壁 御前崎港」という記事を載せている
⇒こちら。
県が御前崎港に設置し、5年前に稼働を開始した風力発電施設「ウインクル」が、昨年12月からずっと停止したままだという内容である。
落雷が原因で故障した後、約4000万円と見積もられている修理費の捻出や、修理のための技術者の手配ができないため「復旧のめどは立たない」のだという。
この風車はデンマークのVestas社製で1950kw級の大型風車。2004年3月に4億5000万円をかけて完成した。
当初はこの風車による発電で御前崎港を「エネルギー自給型港湾」にすると言っていたのだが、風が吹かなければ発電しない風力発電を御するだけの力は自治体には当然なく、結局は電力会社への売電に切り替えた。「港湾で使う電気は電力会社から別に買っている」。
安易なイメージ先行で建ててしまい、それがどれだけ有効なのかを検証することもなく、出力変動への対応など、面倒、迷惑なことは電力会社に押しつけた形だ。
電力会社は、風車からの電気は強制的に高い値段で買い取らなければいけない。法律で決められてしまったので従わざるをえない。しかし、電気が余っているときに急に風車から電気を送られてきても迷惑なだけで、本音では、こうした「余計なこと」はこれ以上しないでほしい、というところだろう。出力調整をしている部署では、24時間体勢で職員が各発電所の出力を調整して需要に合わせているが、風力発電はどのタイミングでどれだけの電力を生み出すのか予測がつかないため、有効利用は極めて困難だからだ。
さて、今回の停止は、昨年12月28日からずっと続いているという。
昨年12月5日に「落雷を受けた可能性がある」とのことで、その後は「動いたり動かなかったりを繰り返した後、同28日に完全停止した。心臓部分にあたる発電機が焼損したため」だそうである。
発電機の焼損となれば、ナセル部分(羽根の中心部にあたり、発電機もここに収納されている)の完全交換ということになるのだろうか。
メーカー保証期間(2年)が過ぎているため、補修費約4000万円は、保険金と税金でまかなわなければならない。
保険金で補修費の半分ほどが出るらしいが、残り約2000万円のやりくりができない。(これだけ事故が続くと、今後、保険会社の風車に対する税金料率も跳ね上がるだろう)
さらには、金の問題とは別に、Vestas社製の巨大風車となれば、修理のための部品調達や修理を担当する専門技術者も海外へ発注することになり、そのへんのノウハウも県の担当者にはどうやらないらしい。
無風状態から台風による暴風など、変動が激しい日本の気候風土に耐えられる大型風車を作ることは容易ではない。
ここの風車だけでなく、日本国中、あちこちで風車の羽根が折れて飛散したとか、根本から倒れたといった事故は枚挙にいとまがない。
東伊豆のCEF社が設置した風力発電施設は、テスト運転中に早々と羽根が折れる事故を起こし、その後、長い間「点検中」ということで止まっていた。再稼働後、またすぐに羽根が折れ、現在も止まっている。
で、動いている時間は、付近の住民に頭痛や睡眠障害、鼻血など、深刻な健康被害を与え、住民の一部は、夜寝るために別にアパートを借りたり、クルマで自宅から離れて車中泊を繰り返したりしていた。
それを考えれば、さっさと事故を起こしてずっと止まっていてくれたほうがよほどマシだが、さて、自治体は自ら設置、または誘致したこれらの巨大公害発生装置にどう対処するのだろうか。
風車の耐用年数は17年とされている。
今後、故障と修理を繰り返しながらだましだまし運転を続けたとしても、20年後には撤去しなければならない。御前崎の風車は県が設置したのだから、そのときの撤去費用も、当然、県の公金(税金)でまかなうことになるだろう。設置してから撤去までの期間の収支はどうなるのか、見ものである。
御前崎港風車の売電収入は、設置した2004年度は約5700万円だったそうだが、2年間保証の切れた2006年度からは、故障のたびに部品調達費用などがかかる上に稼働時間も減り、昨年度は1377万円にとどまっている。
昨年12月からずっと動いていないのだから、今年は今のところゼロである。簡単に修理もできないとなれば、これから先もしばらくは発電量ゼロが続くだろう。
ここで気をつけてほしいのは、風力発電施設の売電金額合計は、この
金額分の電力が有効に使われたということを示すわけではない。電力会社が、買い取らざるをえないので、嫌々その金額を支払わされたということにすぎない。
エコだなんだとお題目を唱えて、「よきこと」のために税金を使っているかのような情報コントロールが毎日されているが、これらの税金は、環境破壊と健康被害の元凶を生み出すために投入されている。
そうして無理矢理推進した風力発電施設から電力会社が「風が吹いたときだけ」強制的に買い取らされる電気が生み出す非効率は、電力料金全体を押し上げるが、それを負担するのは電気料金を払っている我々である。破壊された環境によって、水源を失うなどの被害を受け、風車病で住めない土地にされてしまう住民は、二重三重の被害者である。
御前崎港のウインクルに話を戻せば、建設費のうち、約2億6000万円は県債(借金)だが、その償還も計画通りに進んでいない。
こういうもののためにこれ以上税金を投入するのは馬鹿げている。
CEFや電源開発(Jパワー)系の風力発電事業者が行っている風車ビジネスにしても同じことだ。
故障、修理を繰り返し、動いている間は周囲の住民に「風車病」被害を与え、20年後には撤去費用が捻出できず、巨大なゴミとして放置されることになるだろう。
これのどこが「エコ」なのか、「グリーン電力」なのか。
税金投入をやめれば、こんな馬鹿な事業をやろうという者はいない。
これから政権を取ろうとしている民主党には強く言っておきたい。これこそ「税金の無駄遣い」「不正使用」の典型である。
政権を取る前に、環境を破壊し、税金を捨てているエコビジネスの実体を見抜く勉強をしていただきたい。

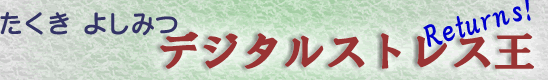


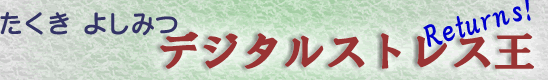


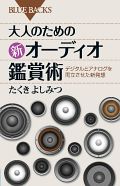
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)