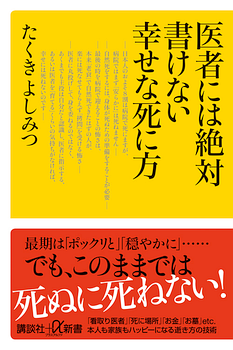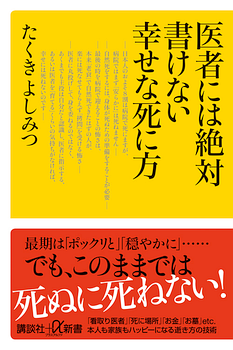医者には絶対書けない幸せな死に方
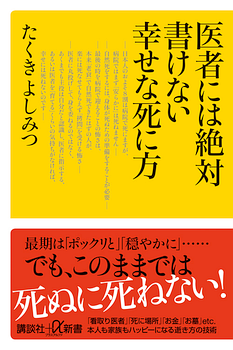 (たくき よしみつ・著 講談社プラスα新書) 立ち読み版
(たくき よしみつ・著 講談社プラスα新書) 立ち読み版
- 書名:医者には絶対書けない幸せな死に方(講談社プラスα新書)
- 発売:2018年1月18日
- 著者:たくき よしみつ
- 種別:新書 224ページ
- 版元:講談社、2018.01.18
- ISBN 978-4-06-291514-4
- 価格:840円+税
- 看取り医、死に場所、お金、認知症、施設の裏事情、お墓……本人も家族も幸せになる「逝き方の技術書」







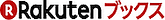
「幸せに死ぬ」ための「知識」と「技術」
ほとんどの人は「苦しまず」「穏やかに」「ポックリと」死にたいといいますが、運任せにしてうまく死ねる人はほとんどいません。
日本人のおよそ8割は病院で死にますが、なまじ延命治療技術が発達してしまったため、病院のベッドに何か月も縛りつけられたまま拷問のような状態で死を迎える人がたくさんいます。
実際、私の母はそういう死に方でした。
脳細胞が壊れ、もう回復の見込みはまったくないのに、意識はあり、栄養経管をつけられ、唯一動かせる左手は縛り付けられたまま、無表情に私を見つめる姿を忘れることができません。そうなったら最後、本人はもちろん、家族にも何もできないのです。
日本が世界でも稀に見る超長寿・超高齢国家になった今、「死に方」「死に場所」「死に時」を間違えることほど恐ろしいことはありません。最悪の死に方を避けるには「具体的に」どうすればいいのか──その「死ぬ技術」について、さまざまな方向から検証し、提案したのが本書です。
さらには、多くの場合、自分がその時を迎える前に、親を「幸せに死なせる」技術として予習しなければならなくなります。本書はそうした視点からも書いています。
「死に方」についての本は医療関係者や宗教関係者によって書かれることが多いのですが、医療や宗教の現場とは無関係な作家という立場で、体裁を繕わず、本音で、踏み込んで、あるいは一線を「踏み越えて」書きました。
医師や病院とうまくつき合う技術、癌や不治の病を宣告されたときの心得、認知症を乗り越える技術、老後を乗り切るための経済学、介護保険や介護施設の基礎知識と裏事情、「死に場所」の見つけ方、最後は積極的安楽死についても、逃げずに「具体的に」考察しています。
頭のはっきりしている今のうちに「幸せに死ぬ技術」を学んだ上で、残りの人生を精一杯ポジティブに生ききりましょう。
何もしなければひどい死に方が待っているのですから。
内容紹介
医者には絶対書けない幸せな死に方
1 死に方の理想と現実
現代では病院で死ぬ人が多いため、死が見えにくくなっている。著者が実際に体験した知人や親族の死の実例も交えながら、「現代日本人の死に方」の実態を紹介。
● 自力で生きられない期間が10年
● 老衰ではなかなか死ねない
● 病院で「拷問死」させられる恐怖
● 癌より怖い脳卒中
● 母の最後──病院で苦しんだ末に
● 死ぬまで知性を働かせることの難しさ
● 家族を病院から取り戻せるか
● 伯母の見事なまでのきれいな死
● 永井明さんの潔い旅立ち
● 穴吹史士さんの残された人を思いやる心
2 医師・病院と正しくつき合う技術
死は周囲の人たちや医師たちとの関係の中で進む「共同作業」であり、自分ひとりで死に方を決めることは極めて困難。中でも医師・病院とのつきあい方は重要な「技術」だ。
● 病院の「90日ルール」
● 「看取り」を巡る医療機関と国の攻防
● 「投薬センス」のある医師を選べ
● 最後まで病院に頼る人
● アクティブQOLとパッシブQOL
● 終末期ではQOL重視の医者を選べ
● 「看取り医」を見つける困難さ
● 看取り医がいなければ「育てる」
3 癌で死ぬという解
日本人の半数以上は癌になる。最後の最後までありとあらゆる治療を試す人もいれば、一切の治療を拒否する人もいる。癌とどう向き合えばいいのかを、極力合理的に考察する。
● 癌にならない人のほうが少ない
● 癌は予防できるのか
● 猫と犬に助けられて生きる
● 癌検診は必要か
● なぜ医者は癌で死にたいと思うのか
● 自分の死を事前に知らせるべきか
● 癌治療のやめ時と病院からの逃げ時
4 本当にアルツハイマーなのか?
身体は動くのに頭が惚けてしまう状態は、人によっては死ぬよりも恐ろしいこと。認知症とどう向き合えばよいのか。自分がなる場合と、家族(配偶者や親)がなる場合の両方を考える。
● 「失う」ことを極度に恐れない
● 老いをパワーに変える技術
● 難しい認知症診断
● 医師の「アリセプト処方依存症」問題
● 「匙加減」をしない投薬で殺される
5 実録・認知症の親と向き合う
認知症は、本人よりも介護する家族が大変な苦労を強いられる。筆者が実際に体験した「認知症の親との向き合い方」を紹介。
● 「別人」になりかわる境界
● 初期の認知症は家族でも気づけない
● 「買い物依存症」で老後資金を使い果たす
● 家族崩壊
● 親のXデーは死んだ日ではない
● 買い物依存症+認知症の合わせ技
● 脳の病なのか「心」の病なのか
● 心の飢餓感が生む生活破綻
6 大切な老後資金を奪われないために
高齢者の資産を狙うのは振り込め詐欺などの犯罪者たちだけではない。「合法的」に高齢者の資産を狙って搾取する「ビジネスモデル」の実態を知ったうえで、なけなしの老後資金を守る技術を学ぶ。
● 高齢者を食い物にする経済活動
● 弁護士も群がる認知症老人資産
● バブル期の「お宝保険」を狙う手口
● 家族も被害者になる特殊詐欺の怖さ
● 生前贈与という「預金」方法
● 成年後見制度の恐ろしさ
7 老後破産しないための経済学
「老後破産」をしてしまったら、幸せには死ねない。親の介護で金と体力を奪われ、自分の寿命を縮める人たちも急増している。少しでも金を節約して楽しく生き延びるための技術を紹介。
● 80代の親を60代の子が面倒みる時代
● 「2025年問題」は乗り切れない
● 老後破産が起きる原因
● 再就職・転職は考えない
● 年老いてからの「住み替え」術
● 「世帯分離」という裏技に追い込まれる家族
● 「マイナス遺産」から逃れる
● ゴミ屋敷処分問題
● 葬儀の負担は極力減らす
● 墓というやっかいな「遺産」
● 遺骨はゆうパックで送れる
● 合理的思考で老後の生活水準を保つ
8 死に場所としての施設を見つける技術
自宅では死ねない(暮らせない)状況になったときは介護施設に入るのが一般的な解だが、どんな施設をどのように利用できるのか。筆者自身の経験も含め、必要な情報をまとめる。
● 「家で死にたい」親と「家で死なせたくない」家族
● 家族と同居の老人のほうがストレスが多い?
● 初めての介護保険申請
● 特養や老健を死に場所と考えるな
● 特養でも月に20万円!?
● 特養に入るための技術
● ベッドは空いていても介護スタッフがいない
● 「今どきの特養」とは
● 常態化している「施設のグレーゾーン利用」
9 「ここで死んでもいいですか?」
介護施設の種類や介護保険のシステムは極めて複雑。そこは「死に場所」としてふさわしいのか、そもそもそこで死なせてくれるのか。一般には知られていないデリケートな要素、見えにくい「スペック外」の問題を明らかにする。
● 特養に置いてもらえなくなった父
● 天国も地獄もある有料老人ホームとサ高住
● 介護保険限度額ビジネスモデルの害
● ダメ医師を押しつけるダメ施設
● 介護スタッフの激務は限界を超えている
● 東南アジア人介護スタッフのいる施設はよい施設
● 「地域包括ケアシステム」の欺瞞性
● 「ここで死んでもいいですか?」と訊いてみる
● 「日本一小さなホーム」に入る
● 優良お泊まりデイという贅沢な選択
● 幸せに死ねるかどうかは周囲の人次第
10 死に方・死に時は選べるのか
日本では積極的安楽死は認められていない。それを理解した上で、死に方・死に時を自分で選ぶことは可能なのか……最後はタブーの領域に踏み込んで、積極的安楽死(自殺)について、冷徹な考察を試みる。
● 「主役」の尊厳を軽視する日本の医療・介護現場
● 日本では「積極的安楽死」は殺人罪
● 延命措置は一旦始めるとまずやめられない
● 生きる価値をどこに置くかで「死に時」も変わる
● こんな自殺はしてはいけない
● 凍死という死に方
● 死ぬ前のチェックリスト
■あとがき ──愛する技術と死ぬ技術

以下のいずれからでもご購入できます(Click)







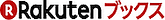
Homeへ たくき よしみつ 著作リストへ