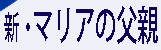定期購読しているメルマガの中に
「ほぼ日デリバリー版」がある。
「ほぼ日」は「ほぼにち」と読む。糸井重里さんがやっている
「ほぼ日刊イトイ新聞」の略称である。スタート直後はどうだったのか知らないが、今は多くの(多分)制作スタッフを抱える巨大なサイトに成長している。
僕が特に気に入っているのは
「ほぼ日式声に出して読めない日本語。」というコーナーで、毎日ではないが、1週間とか2週間に一度アクセスしてはまとめ読みしている。
9割方読めるのだが、お目当ては秀逸な「例文」。
うんちく
【蘊蓄】
<例文>
双眼鏡の歴史について
延々とうんちくを述べたあと、
突然のプロポーズ。
なんていう例文がいっぱい楽しめる。誰が書いているんだろうと、いつも感心している。糸井さん自身なら「さすが」だし、糸井さん以外の誰かさんなら「恐るべし」である。
で、「ほぼ日」が発行しているメルマガ「ほぼ日デリバリー版」で、最近、食べ物と食べ方についての投稿が続いていた。世の中には、のびたラーメン、しけった煎餅、牛乳かけご飯、ふやかしたキャラメルコーン……といったものを心から愛している人たちがかなりたくさんいるということを改めて知った。
のびたラーメンが好きだなどということは、一般的には自慢げに口にできない。気むずかしい店主の前でそんなことを言ったら「お客さん、金はいらねえ。帰ってくんな」と怒られてしまうかもしれない。
それだけに、のびたラーメン好きの人が、自分と同じ「のびたラーメン好き」の人に出逢ったときの喜びはひとしおだろう。
しかし、自分と同じ味覚を持った人間が、他の部分でも気が合うとは限らない。のびたラーメン好きの人が自分と同じのびたラーメン好きの人と出逢った後、その人がこの上なく嫌なやつだと分かったときは、一転して深い悲しみを味わうことになるかもしれない。
味覚だけではない。あらゆる趣味、嗜好、感覚について、人間は基本的に孤独である。
同じ色の同じクルマを運転する人が、窓から火のついたままの煙草をポイ捨てするのを見たとき。
あまり人に知られていない作家の作品について、思いがけず意見が一致して盛り上がった会話をした後で、その「同士」が、遊びで野生動物を殺して剥製にするという趣味を楽しそうに語り始めたとき。
「いつもここから」の持ちネタではないが、まさに「哀しいとき~♪」である。
聴覚に関しては、かなり決定的な孤独感を味わうことが多い。
音楽の趣味は人それぞれだが、それは「聴覚」、言い換えれば音感が違うからだ。
聴覚の能力は幼いときに決定してしまい、大人になってから変えることは難しい。言葉がよい例で、幼児は誰が教えるでもなく周囲の会話を聴いて言語能力を身につけるが、大人になってから別の言語を完全にマスターすることは非常に難しい。
メロディに対する音感も同じで、子供の頃に叩き込まれた音感教育がどのようなものだったか、あるいはそうした訓練をされたか否かが、一生を通じて自分が感動するメロディを大体決めてしまう。
僕の場合は、幼児のとき、シューベルトやモーツァルトなどの歌曲や小品など、明解なドレミファ音階に根ざしたメロディを「移動ド」階名教育と一緒に何度も繰り返して聴かされたため、音感がヨーロッパ型というか、分かりやすい西洋音楽型に固まってしまった。言い換えれば、ドレミファで歌える名曲が心地よさとして刷り込まれてしまった。
そのため、大人になってからジャズやボサノバのテンションをどう受け入れていいのか戸惑った時期もある。心地よく感じるようになるには、少し時間がかかった。ジョビンの『波(WAVE)』は名曲だが、あれはドレミファでは歌えないものね。長い間、ただのBGMのように聞き流していた。流麗ではあるけれど、魂が震えるような感動は得られないメロディ。
でも今は、『波』の凄さが分かる。BGMだなんてとんでもない。『波』が流れてくると、思わず聴き入ってしまう。
『赤とんぼ』や『上を向いて歩こう』も凄いメロディだが、ああいうドレミファで完全に歌えるメロディの中での美に加えて、自分の脳の中で新しい「美意識」「感動」の領域が増えたのである。
メロディというものを意識することなく大人になった人の中には、音楽はサウンドそのものであると感じる聴覚を持っている人もいる。単純なリズムの繰り返しの中に身を委ねることが最上の心地よさと感じる人もいる。かと思えば、速弾きのスリルこそ音楽の醍醐味だと感じる人もいる。
昔、あるアメリカ人(アングロサクソン系だと思う)ミュージシャンに僕の曲を聴かせたときの彼の反応が忘れられない。
「これはすごい。完璧な音楽だ。きみの音楽はモーツァルトと同じ種類の音楽だね。すばらしい! でも、ぼくの趣味じゃない。ぼくはもっと無秩序な音楽が好きなんだ。言い換えれば『汚い音楽』にほど興奮するんだ」
そう言って聴かせてくれたのは、まさに混沌としたノイズのような音楽だった。
彼の聴覚は、モーツァルト的メロディ感ではなく、混沌とした音の泥沼のような音楽こそ価値のあるものと判別すると知って、びっくりした。理屈ではなく、本当に聴覚としてそう感じているのだろう。
その男性とは一度だけ、小一時間ほど会っただけだが、底抜けに「いいやつ」であることは間違いなかった。正直で、純粋で、優しくて、知的で、紳士だった。でも、彼は僕の作った音楽(というよりもメロディ)を認めてくれても、僕のメロディで気持ちよくなることはない。その溝が哀しかった。
聴覚の壁について、もっと分かりやすいたとえ話をしてみる。
無人島に男3人が流れ着く。(男女だと余計なファクターが入るので、ここは同性だけということにしておく)
日本語しか話せない日本人が二人。韓国語しか話せない韓国人がひとり。お互い、それまでは面識がない。あなたはその日本人のうちのひとりだ。
日本人二人は言葉が通じるからすぐにコミュニケーションがとれる。しかし、すぐにあなたは、もうひとりの日本人がめっちゃくちゃ嫌なやつであることを悟る。
韓国人は逆に底抜けにいいやつだった。言葉は通じなくても、行動のはしばしにそれがうかがえる。でも、哀しいかな、言葉がまったく通じない。
あなたはむしろ韓国人の男と多くの時間を割いてコミュニケーションしたいのだが、できない。
もちろん、時間をかけてお互いがお互いの言葉を教え合うことはできるだろうが、日本人と日本語で話し合うほど、細かなニュアンスまで伝えられるまでにはなかなかいかないだろう。
聴覚の壁というのは、普段はあまり意識しないかもしれないが、実際には残酷な壁として厳然と存在している。
美術的感性の違いも興味深い。
世の中には、抽象表現をまったく受け入れられない人が少なくない。ピカソなんて、誰がなんと言おうが無価値な悪戯書きだと主張する。
もちろん、抽象表現を評価する人の中でも、感性はさまざまに分かれる。クレーとカンディンスキーとどっちが好きかという問いをすると、見事なほどきれいに分かれる。
クレーとカンディンスキーが分かりにくければ、「棟方志功をどう評価するか」でもいい。棟方志功の作品を好きな人、嫌いな人、何も感じない人、いろいろいる。
好きではないが、美術として「分かる」なんていう人もいる。つまり、志功の作品における技術や大胆な手法は評価するが、最終的に作品を見て、自分は特に幸せにはなれない、というようなタイプの人。
もちろん、こうした感性の違いは、学習や経験によって変わっていくことが多いから、生涯不変なものではない。でも、分からない、感じないという人が、一生その感性を持ち続ける(分からない、感じないままである)可能性は非常に高い。
また、芸術や学問をどの程度究めたかということと、基本的な人間性は関係がない。天才芸術家にして殺人鬼という人間はいくらでもいる。
五木寛之氏の小説だったと思うが、初期の頃の作品の中に、ナチスドイツの将校が、ユダヤ人の美少女の肌に入れ墨をし、その皮膚を剥いで電気スタンドの傘にして楽しむというシーンが出てくる。その傘のついたスタンドを灯した部屋で、別の新しい少女を裸にして眺め、酒を飲む。恐怖と絶望にうちひしがれている少女を前に、将校は酔いに任せて部屋の中にあるピアノに向かう。次の瞬間、この世のものと思えないほど美しい音色が部屋中に満ちる……。
そんなシーンがあった。(記憶が曖昧なので、細部は違っているかもしれない。)
音楽をはじめとする芸術の価値と、人間の精神性は何の関係もない、ということを表した場面だ。
すばらしい芸術家がすばらしい人間であるとは限らない。もちろん、優秀な学者が、学生の手本となる人格者であるという必然もまったくない。
できたてよりも、時間が経ってのびきったラーメンのほうが好きだ、という味覚は僕にはよく分からない。でも、しけったコロッケが好きだという程度なら、なんとなく分かる。ソースが染みきって、冷えきって、コロモがしけりきったコロッケをしょぼしょぼと食べるとき、そんなに悪くない気分になることはある。うまく言えないが、「食い物がここにある」という根源的な幸福感は、できたてあつあつサクサクのコロッケをハフハフしながら食べるときより味わいやすいかもしれない……ような気がしないでもないようなあるような……。
しかし、ひとつはっきりしているのは、しけったコロッケが大好きで、サクサクのコロッケにはまったく幸福感を感じないという人が料理人になったときの孤独感は相当なものだろうということだ。
僕の書くメロディはしけったコロッケなのか?
よく分からない。
かつてはあつあつサクサクだったが、今はしけりつつある、ということもありえるだろう。それは大きな問題ではない。
今の僕は、まだ自家製コロッケをおいしく食べられる。これははっきりしている。問題は、自分で作ったものを自分で食べておいしいおいしいと言っている状態。コロッケ店の店主と違って、世界中に自分の作ったコロッケを届けるためには質を落とさなくてはいけない、なんてことはないのだけど、なあ。

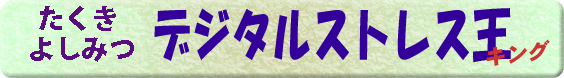


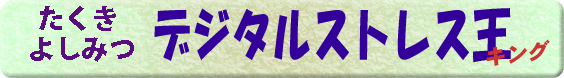



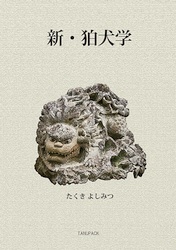
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)