 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ

2020/01/03
種なし葡萄農家と「原理主義者」の話

元日のテーブルの上



階下に降りていくと、Eテレのらららクラシックという番組をBGM代わりに流していて、チェンバロ奏者がこんなことを言っていた。
「バッハは聴衆を喜ばせようというショーマンシップではなく、職人として、この宇宙の摂理を作った神に恥ずかしくないような音楽を作ろうとしていたのだと思います」
……ん?
そのフレーズ、なかなか深いね。
もちろん、その「神」は人によって違う。「職人」という意識があったかどうかも分からない。
しかし、聴衆に媚びない、神に恥じないようなものを作る、というのは「いいね!」。
去年は、「人生死んだ後が勝負」という達観が、達観ではなく、煩悩まみれだと気づいた。その先を意識しないと、創作は続けられないなあと思っていたところに、円丈さんの「人生死ぬときが勝負」「自分を評価できるのは自分しかいない」という手紙が届いた。
で、死んだ後の「この世」に評価してほしいと未練を残すのではなく、自分の中にある宇宙のようなもの、そのわけのわからない価値観のためにメロディの価値を信じる……というような気持ちに切り替えよう、なんて思いながら年を越したところだった。
いいじゃないの、これ。「神に恥じない音楽」を、今年のスローガンにしてみようかな。
それとは別に、「人生死んだ後が勝負」路線(?)は、人生最後の小説が書けるかどうかへの挑戦、という形で継続させられたら、と思う。
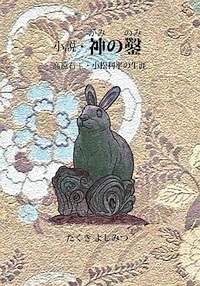

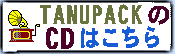
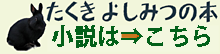

|
|
|---|